

日本のIT人材育成の未来を見据えたプログラミング教育の必要性
日本のIT人材育成の課題と将来ビジョン
2025年1月29日、東京都港区に本社を構えるpaiza株式会社(代表取締役社長/CEO 片山良平)は、自由民主党の政務調査会デジタル社会推進本部において、今後のデジタル人材輩出を目指したプログラミング教育についてプレゼンテーションを行いました。この場では、日本が直面するIT人材の不足、その育成の遅れについて深く掘り下げられました。
IT人材不足の現状と課題
日本国内におけるIT人材の現状は深刻です。今後2030年には最大79万人のIT人材が不足すると予測されており、その中でも特にプログラミングスキルを必要とする分野、AIやデータサイエンスにおいては55万人もの人材が足りないとされています。これは、ただ単にエンジニアの数が不足しているだけでなく、先端技術を扱える技術者の育成が遅れていることを意味しています。
諸外国と比較しても、日本のプログラミング教育の進展は依然として遅れています。特にイスラエルでは1970年代からプログラミング教育に注力し、高校段階で90時間から450時間の教育時間を確保しています。一方、日本の高校では、プログラミングに関する実際の授業時間が10時間以下の例が53.7%を占めているという現状があります。
プログラミング教育における障壁
日本のプログラミング教育が進まない要因は、さまざまです。その一つには、人材や情報、予算の不足が挙げられます。また、学習者自身の目的意識が低いことも問題です。たとえば、大学入学共通テストに新たに導入された「情報Ⅰ」は、必須としている大学が少なく、結果として学習意欲を低下させていると指摘されています。特に文系の大学ではプログラミング教育が不足しており、理系でも専門領域の学習に時間が取られがちで、十分なプログラミング教育を受けることは難しい状況です。
提言と今後の方針
このような状況を打破するためには、まず学校でのプログラミング教育の強化が求められます。具体的には、eラーニング教材の導入やプログラミングサポート講師の活用を進めることで、より多くの学生にプログラミングを学ぶ機会を提供する必要があります。
また、大学入試においてもプログラミングに関する問題を強化し、プログラミングスキルの重要性を認識させることが重要です。このようにして、IT人材が育ちやすい環境を整備することは、将来的な人材確保につながります。
さらに、社会との接続を強化するため、プログラミングスキル試験の実施や新卒エンジニアの採用サポートを行うことで、実際の職場での活躍が期待できる人材の輩出に努めるべきです。
まとめ
日本のIT人材の確保と育成は急務です。技術革新が進む現代において、プログラミング教育の重要性はますます高まっています。paiza株式会社は、これらの活動を通じて、より多くの人々がITの世界で活躍できるような環境を整え、デジタル人材の育成に寄与していくことを目指しています。今後の一層の取り組みに期待が寄せられています。

会社情報
- 会社名
- paiza株式会社
- 住所
- 東京都港区虎ノ門2-3-17虎ノ門2丁目タワー18F
- 電話番号
トピックス(IT)


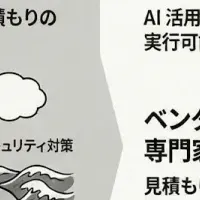



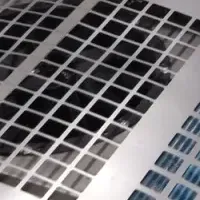


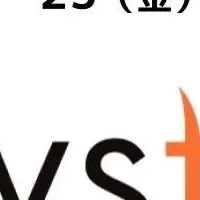
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。