

石田組、武道館公演で70年代ハードロックからクラシックまで!8300人の観客を熱狂の渦に巻き込む
2024年11月10日、結成10周年を迎えた弦楽合奏団「石田組」が、念願の日本武道館公演を開催した。8300人の観客で満員の武道館は、石田組の演奏と個性的な演出に熱狂した。
開演前に最も気になっていたのは、石田組が武道館という大舞台でどのような演奏を聴かせてくれるのかということだった。クラシック音楽の会場としては最大規模のサントリーホールを昨年2ステージこなし、追加公演も行ったという石田組。最小人数での弦楽アンサンブルを会場の隅々まで響かせることに拘りを持つ彼らが、武道館という広大な空間をどのように満たすのか、期待が高まっていた。
ステージは左右に巨大スクリーン、バックには武田双雲による「石田組」のロゴが掲げられ、無数の照明が設置されていた。武道館という空間を最大限に活かした舞台設計に、期待はさらに膨らむ。客電が落ちると、歓声とともに紫色の灯りの中に石田組のメンバーが登場。低く響くイントロは、なんと布袋寅泰の「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」だった。ステージ中央に後光が差すと、石田泰尚がゆっくりと登場。メンバー全員がサングラスをかけているという、予想外の演出に観客は一気に引き込まれた。
その後も、レッド・ツェッペリンの「天国への階段」、レインボーの「スターゲイザー」など70年代ハードロックの名曲が続き、会場は熱気に包まれた。これらのバンドは、後半のU.K.を除いて、いずれも武道館でライブを行ったことがある。石田組は、音楽を通して各メンバーの個性を際立たせる演出にも長けており、「天国への階段」では、辻本玲(チェロ)、中村洋乃理(ヴィオラ)、佐久間聡一(第1ヴァイオリン)、双紙正哉(第2ヴァイオリン)といったトップ奏者によるソロが聴衆を魅了した。
クラシックナンバーでは、ラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」、ファリャの「火祭りの踊り」、ビゼーの「ファランドール」などが演奏され、エキゾチックな雰囲気が会場を包んだ。「ファランドール」は、この日の最初のピークを飾った。
演奏を聴きながら、石田組のこだわりを感じたのは音響のセッティングだった。メンバー全員の楽器にピックアップマイクが付けられ、武道館という広大な空間全体に音がしっかりと届いている。音響スタッフの緻密なオペレートにより、弦楽器のナチュラルさを保ちつつ、弓が弦を擦る音、スタッカートやピツィカート、石田の呼吸やカウントの声まで、臨場感を持って伝わってきた。
前半はクイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」「ボーン・トゥ・ラブ・ユー」で締めくくられた。石田組のクイーンナンバーは、原曲の再現度が高く、聴き惚れてしまうほどだった。特に「ボーン・トゥ・ラブ・ユー」では、照明によってクイーンのミュージックビデオを再現したかのような演出も見られた。
後半は、アストル・ピアソラの「アディオス・ノニーノ」、「タンゲディアⅢ」、「リベルタンゴ」など、タンゴ作品が続いた。タンゴ奏者としても高く評価されている石田だが、ここではクラシック奏者としての矜持を魅せ、ソロ演奏やアンサンブルで観客を圧倒した。
三浦一馬(バンドネオン)との共演も圧巻で、熱気に満ちた会場に、北野武映画のような淡く濃いブルーの照明が差し込むと、石田の物哀しいソロに導かれて「ゴッド・ファーザー・メドレー」が始まった。文句なしの名演で、同時に石田のアウトローへの憧憬を感じさせるひと時でもあった。
ここから本編ラストに向けて、演奏はさらにヒートアップしていく。U.K.の「シーザー・パレス・ブルース」、レッド・ツェッペリンの「カシミール」、そしてディープ・パープルの「紫の炎」と、名曲が次々と披露され、演奏に呼応するかのように舞台演出も切れ味を増していく。
そして「紫の炎」では、至る所で火の手が上がった。火を吹くクラシックコンサートは初めてだったが、燃え盛るステージで演奏された「紫の炎」は、ヴィヴァルディの協奏曲のような様式美を感じさせた。ロックとクラシックを融合させようとした作曲者のリッチー・ブラックモアが目指した境地に近かったのかもしれない。オープニングと同様、観客は呆気にとられながら本編が終了した。
すでに予定の終演時間を超えていたが、石田組らしい贅沢なアンコールが始まった。まずはヘスの「ラヴェンダーの咲く庭で」という愛らしい旋律の小品が演奏された。しかし、石田泰尚以下、メンバーはディープ・パープルのテンションのままステージに戻ってきたようで、何ともチャーミングな演奏だった。
「銀河鉄道 999」では、観客がスマホの灯りを点灯し、武道館全体を照らし出した。石田は「ありがとう」を演奏する前に、胸に「ありがとう」とプリントされたTシャツに着替えて登場。アンコールのラストは、今年再結成を果たしたオアシスの「ホワットエヴァー」で、左右のキャノン砲から金銀のテープが放たれ、石田組の武道館公演は幕を閉じた。
今回の公演は、クラシックコンサートとしては派手すぎるという声も上がるかもしれない。しかし、書かれているように、確かに普段では味わえないような楽しさに満ちた公演だった。ヴィオラの生野正樹がMCの中で、今回のコンサートがどれほど特別な場なのかについて真摯に語っていた。クラシックの演奏家は、これほどショーアップされた舞台で演奏することはまずない。数百年来積み重ねられてきたステージマナーに則って、楽譜に書かれた音楽を何度も奏でていくことで歴史を繋いできた。
彼らにとって、それぞれのエキスパートが演出を施していく今回のコンサートは、普段と異なる祝祭的な空間だったことは間違いない。だが、石田組の演奏は、いつもと変わらない誠実なトーンだった。「ホワットエヴァー」を演奏する前に石田が何気なく言った「みなさん、気をつけて帰ってください」という一言を思い出す。聴衆が明日からそれぞれの生活に戻るように、出演者たちもそれぞれのオーケストラやリサイタル活動に帰っていき、各地で演奏を続けていく。そこでは火の手は上がらないかもしれないが、石田組が体現する生きた音楽を聴くという愉しさが息づいているに違いない。「気をつけて帰ってください(そしてまた会いましょう)。」武道館という大舞台で、石田組は普段通りに最高の演奏を届けてくれた。それは、これからの楽壇の未来に希望を灯す素晴らしい一夜であった。









開演前に最も気になっていたのは、石田組が武道館という大舞台でどのような演奏を聴かせてくれるのかということだった。クラシック音楽の会場としては最大規模のサントリーホールを昨年2ステージこなし、追加公演も行ったという石田組。最小人数での弦楽アンサンブルを会場の隅々まで響かせることに拘りを持つ彼らが、武道館という広大な空間をどのように満たすのか、期待が高まっていた。
ステージは左右に巨大スクリーン、バックには武田双雲による「石田組」のロゴが掲げられ、無数の照明が設置されていた。武道館という空間を最大限に活かした舞台設計に、期待はさらに膨らむ。客電が落ちると、歓声とともに紫色の灯りの中に石田組のメンバーが登場。低く響くイントロは、なんと布袋寅泰の「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」だった。ステージ中央に後光が差すと、石田泰尚がゆっくりと登場。メンバー全員がサングラスをかけているという、予想外の演出に観客は一気に引き込まれた。
その後も、レッド・ツェッペリンの「天国への階段」、レインボーの「スターゲイザー」など70年代ハードロックの名曲が続き、会場は熱気に包まれた。これらのバンドは、後半のU.K.を除いて、いずれも武道館でライブを行ったことがある。石田組は、音楽を通して各メンバーの個性を際立たせる演出にも長けており、「天国への階段」では、辻本玲(チェロ)、中村洋乃理(ヴィオラ)、佐久間聡一(第1ヴァイオリン)、双紙正哉(第2ヴァイオリン)といったトップ奏者によるソロが聴衆を魅了した。
クラシックナンバーでは、ラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」、ファリャの「火祭りの踊り」、ビゼーの「ファランドール」などが演奏され、エキゾチックな雰囲気が会場を包んだ。「ファランドール」は、この日の最初のピークを飾った。
演奏を聴きながら、石田組のこだわりを感じたのは音響のセッティングだった。メンバー全員の楽器にピックアップマイクが付けられ、武道館という広大な空間全体に音がしっかりと届いている。音響スタッフの緻密なオペレートにより、弦楽器のナチュラルさを保ちつつ、弓が弦を擦る音、スタッカートやピツィカート、石田の呼吸やカウントの声まで、臨場感を持って伝わってきた。
前半はクイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」「ボーン・トゥ・ラブ・ユー」で締めくくられた。石田組のクイーンナンバーは、原曲の再現度が高く、聴き惚れてしまうほどだった。特に「ボーン・トゥ・ラブ・ユー」では、照明によってクイーンのミュージックビデオを再現したかのような演出も見られた。
後半は、アストル・ピアソラの「アディオス・ノニーノ」、「タンゲディアⅢ」、「リベルタンゴ」など、タンゴ作品が続いた。タンゴ奏者としても高く評価されている石田だが、ここではクラシック奏者としての矜持を魅せ、ソロ演奏やアンサンブルで観客を圧倒した。
三浦一馬(バンドネオン)との共演も圧巻で、熱気に満ちた会場に、北野武映画のような淡く濃いブルーの照明が差し込むと、石田の物哀しいソロに導かれて「ゴッド・ファーザー・メドレー」が始まった。文句なしの名演で、同時に石田のアウトローへの憧憬を感じさせるひと時でもあった。
ここから本編ラストに向けて、演奏はさらにヒートアップしていく。U.K.の「シーザー・パレス・ブルース」、レッド・ツェッペリンの「カシミール」、そしてディープ・パープルの「紫の炎」と、名曲が次々と披露され、演奏に呼応するかのように舞台演出も切れ味を増していく。
そして「紫の炎」では、至る所で火の手が上がった。火を吹くクラシックコンサートは初めてだったが、燃え盛るステージで演奏された「紫の炎」は、ヴィヴァルディの協奏曲のような様式美を感じさせた。ロックとクラシックを融合させようとした作曲者のリッチー・ブラックモアが目指した境地に近かったのかもしれない。オープニングと同様、観客は呆気にとられながら本編が終了した。
すでに予定の終演時間を超えていたが、石田組らしい贅沢なアンコールが始まった。まずはヘスの「ラヴェンダーの咲く庭で」という愛らしい旋律の小品が演奏された。しかし、石田泰尚以下、メンバーはディープ・パープルのテンションのままステージに戻ってきたようで、何ともチャーミングな演奏だった。
「銀河鉄道 999」では、観客がスマホの灯りを点灯し、武道館全体を照らし出した。石田は「ありがとう」を演奏する前に、胸に「ありがとう」とプリントされたTシャツに着替えて登場。アンコールのラストは、今年再結成を果たしたオアシスの「ホワットエヴァー」で、左右のキャノン砲から金銀のテープが放たれ、石田組の武道館公演は幕を閉じた。
今回の公演は、クラシックコンサートとしては派手すぎるという声も上がるかもしれない。しかし、書かれているように、確かに普段では味わえないような楽しさに満ちた公演だった。ヴィオラの生野正樹がMCの中で、今回のコンサートがどれほど特別な場なのかについて真摯に語っていた。クラシックの演奏家は、これほどショーアップされた舞台で演奏することはまずない。数百年来積み重ねられてきたステージマナーに則って、楽譜に書かれた音楽を何度も奏でていくことで歴史を繋いできた。
彼らにとって、それぞれのエキスパートが演出を施していく今回のコンサートは、普段と異なる祝祭的な空間だったことは間違いない。だが、石田組の演奏は、いつもと変わらない誠実なトーンだった。「ホワットエヴァー」を演奏する前に石田が何気なく言った「みなさん、気をつけて帰ってください」という一言を思い出す。聴衆が明日からそれぞれの生活に戻るように、出演者たちもそれぞれのオーケストラやリサイタル活動に帰っていき、各地で演奏を続けていく。そこでは火の手は上がらないかもしれないが、石田組が体現する生きた音楽を聴くという愉しさが息づいているに違いない。「気をつけて帰ってください(そしてまた会いましょう)。」武道館という大舞台で、石田組は普段通りに最高の演奏を届けてくれた。それは、これからの楽壇の未来に希望を灯す素晴らしい一夜であった。









会社情報
- 会社名
- (株)キョードーメディアス
- 住所
- 電話番号
トピックス(音楽・ライブ・コンサート・ラジオ・アイドル・フェス)




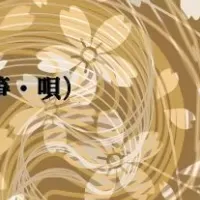

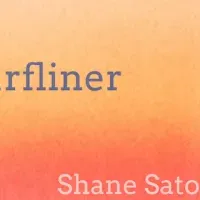



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。