

原子力発電の再活用と新増設に向けた提言が提示された理由
原子力発電の再活用と新増設に向けた提言が提示された理由
2025年以降の環境において、エネルギー供給の安定性はますます重要視されています。社会保障経済研究所(IIGSSP)は、これに伴い日本のエネルギー需給の在り方についての提言を発表しました。その主な内容は、原子力発電の再活用に加え、新しい発電所の増設を推奨するものでした。この提言には、国際的な産業競争力や地域経済の強化を目指した背景があります。
エネルギーの安定供給と原子力の役割
日本はエネルギー資源の大部分を輸入に依存しており、これまでエネルギー価格の安定化を目指して様々な施策を講じてきました。しかし、国際情勢の不安定や自然災害を受け、ガソリンや電気・ガス料金の高止まりが続いています。特に、311震災以降の原子力発電に関する規制が厳しく、なかなか発電所の再稼働が進まない現状があります。
311震災以降、原子力発電は再稼働が進まない中、エネルギー供給のニーズは高まる一方です。これを解決するためには、既存の原子力発電所をフル活用し、新たに運用可能な発電所の増設を進めることが求められます。原子力の最大活用により化石燃料の輸入を削減し、国富を地域経済に活かすことが可能となるのです。
原子力規制の改革の必要性
提言の中では、現在の原子力規制行政についても見直しが必要だとされています。石川和男氏が代表を務める社会保障経済研究所は、原子力規制委員会のあり方に疑問を呈しています。現在の「独立」性の強化がおそらく過剰な規制につながっているとの見解です。原子力事業は国策であり、その安全性や事業の運営は国全体で責任を持つべきです。このため、原子力規制の在り方を早急に改正し、政治的な判断が行えるようにすべきだと提唱しています。
地元同意から国政判断へ
また、原子力発電所の再稼働や新設に関する現行の「地元同意」制度の見直しも必要です。現在、電力事業者が規制委員会から許可を得ても、地元知事の許可が必要とされてしまっている実情があります。これでは国のエネルギー政策が地元の事情に左右されることになります。そのため、最終判断は内閣総理大臣が行えるように法律の整備が求められています。
新増設の必要性と具体化
さらに、新たに原子力発電所の新増設を始めるべきとの意見も示されています。エネルギー需給の観点から、既設の発電所を最大限活用するだけでなく、廃炉後を見越した新式の発電所導入が必須となってきています。脱炭素化の流れの中で、エネルギー供給の安定に向けた取り組みが求められます。
2025年以降のエネルギー政策がどう変化していくのか注目される中、社会保障経済研究所の提言は一つの重要な指標となりそうです。エネルギー問題は私たちの生活にも直結します。今後、どのように日本のエネルギー政策が展開していくのか、その行方を見守る必要があります。

会社情報
- 会社名
- 社会保障経済研究所
- 住所
- 東京都千代田区大手町2-1-1-20F
- 電話番号
トピックス(地域情報)



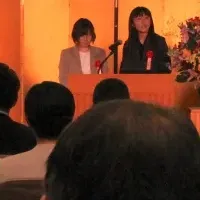

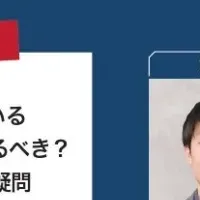
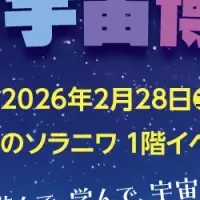



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。