

こどもの権利向上を目指す新プロジェクトが始動!人権週間に特別動画公開
こどもの権利法の理解が進む新たな試み
2023年12月4日から10日にかけて開催される第76回人権週間に際し、公益財団法人日本ユニセフ協会は「こどものけんりプロジェクト」の一環として、法務省および全国人権擁護委員連合会と共に特別動画を公開することを発表しました。この動画は、子供たちの権利を理解し、それを普及させるためのもので、特に大きな意義を持っています。
「こどものけんりプロジェクト」とは?
「こどものけんりプロジェクト」は、日本国内で「子どもの権利」の認知度を高め、子供たちにフィットした情報提供を行うことを目的としています。子どもたちが自分の権利を知ることで、自己の尊厳を理解し、お互いの権利を尊重し合える社会を築くことを目指しています。特に、教育の分野では、ユニセフの「子どもの権利を大切にする教育」に基づいた教材の開発が進められています。
スペシャル動画の内容
公開されたスペシャル動画「ジーン&ケーンと一緒に考えよう!『人権週間』と『こどものけんり』」では、応援キャラクターのパペット、ジーンとケーンが法務省の人権擁護局長をインタビューし、分かりやすく人権週間の意義や人権について説明します。こうした形で子供たちに親しみやすく権利を教える試みは、教育環境において新たな風を感じさせます。
日本における権利条約の認知度の現状
このプロジェクトにとって重要な背景は、「子どもの権利条約」の認知度です。最新の調査によると、日本の成人のうち、約50%がこの条約について何らかの認識を持っていますが、実際の理解には大きな格差があります。特に小学校低学年の子どもたちの認知度はさらに低く、これを打開することが急務とされています。子どもたちに自分の権利を正しく理解させることは、彼らのウェルビーイングにも重要です。
こども基本法の施行とその目的
今年、こども家庭庁の創設とともに施行された「こども基本法」は、全ての子どもと若者が幸福に暮らせる社会を目指すもので、権利を尊重し共に育てていく方針が示されています。これにより、子どもと若者が権利の主体であることがようやく広まってきました。この法律は、子どもの権利を守るための基本的な方針を定めているため、非常に重要です。
教育の現場での取り組み
日本ユニセフ協会はこども家庭庁と連携し、約5万の幼稚園や小中高校において、「子どもの権利教育」の普及をナビゲートしています。これにより、教育の現場で積極的に子どもたちの権利を教える機会が増え、多くの子どもたちが自らの権利を学ぶチャンスを得ることができるのです。また、2029年には「子どもの権利条約」の誕生40年を迎えることも視野に入れています。これを機に、さらなる教育の充実を図り、同時に持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取り組みも行われていくでしょう。
まとめ
「こどものけんりプロジェクト」が進める活動は、子どもたちの権利を知るための第一歩となり、自己の尊厳や他者への理解を育む重要な試みです。子どもたちが安心して生活できる社会を実現するため、さまざまな取り組みを通じてその土台を築いていく必要があります。日本の未来を担う子どもたちのために、一丸となって積極的に参加していきましょう。


会社情報
- 会社名
- 公益財団法人日本ユニセフ協会
- 住所
- 東京都港区高輪4-6-12ユニセフハウス
- 電話番号
- 03-5789-2016
トピックス(地域情報)


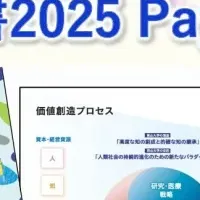
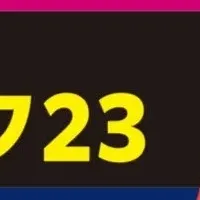






【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。