
最新のHPCI計画推進委員会が国際情勢と計算基盤の未来について議論
最新のHPCI計画推進委員会が国際情勢と計算基盤の未来について議論
令和7年3月31日、文部科学省で第62回HPCI計画推進委員会が開催されました。メンバーには専門家や公的機関の代表が勢揃いし、国際的な情勢や計算能力の進展について多様な意見が交わされました。
委員会の構成
出席した委員には、合田、伊藤(公平)、伊藤(宏幸)、上田、梅谷、小林主査代理、田浦、館山、中川、福澤、藤井主査、朴、棟朝と多彩な背景を持つ専門家が名を連ねます。また、文部科学省の諸職員やアドバンスソフト株式会社、理化学研究所からのオブザーバーも参加し、内容の充実を図りました。
国際情勢の把握
会議では、HPCIに係る国際情勢に関してアドバンスソフトからの報告が行われ、中国の資格と性能に対する疑念が指摘されました。特に、OceanLightが示す94%のLINPACK性能について、実際のデータは信頼性が乏しいとする意見が出ており、情報源の透明性や技術的背景についての検討が必要とされました。
藤井主査は、報告書を修正し適切な情報提供を行うことを提案し、今後の調査で得た質問や意見が活用される旨を伝えました。
次世代技術への期待
続いて、次世代計算基盤を見据えた運営に関する議論も進められました。田浦委員は過去の問題提起を踏まえ、研究開発プログラムの推進を強調。その中でも特にHPC・AI開発支援拠点や次世代技術の支援が重要であると語りました。
梅谷委員からは、運用現場での課題について提起があり、民間企業との連携を促す声も多くの賛同を得ました。これに対して、運用の柔軟性を保ちながら、共同で問題に取り組むことが必要であるとの意見が相次ぎ、今後の協力の可能性が示唆されました。
資源確保の重要性
さらには、アプリケーションへの資源確保が委員から提起され、持続可能な投資が求められました。特に、国内外でのAI技術の進展に伴い、日本の投資が競争力に影響を及ぼすとの見解が共有され、積極的な資金投入が必要であるとの認識が広がりました。
HPCIの未来と結論
今後のHPCI計画に関しては、特に算出したデータを基にしたフィードバックループを形成し、技術の進展に合わせて柔軟に対応していくことの重要性が認識されました。問合せ先として、研究振興局参事官(情報担当)付計算科学技術推進室が挙げられ、今後の議論の進展が期待されます。
以上を通して、第62回HPCI計画推進委員会では、国際情勢、次世代技術開発、持続可能な資源確保といった重要なテーマについての活発な意見交換が行われたことが印象的でした。日本がこれからも計算科学の最前線で競争力を維持するためには、委員会での議論を実行に移していく姿勢が求められるといえるでしょう。
トピックス(IT)

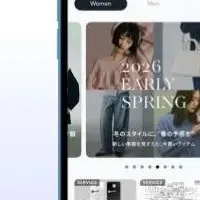




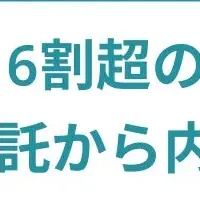
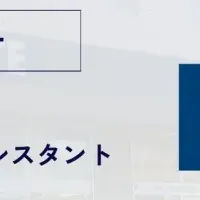


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。