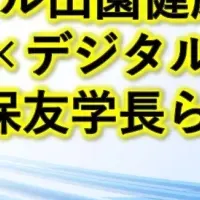

岡山大学が推進するCO2排出量可視化の新たな取り組み
岡山大学が推進するCO2排出量可視化の新たな取り組み
2025年1月20日、国立大学法人岡山大学は、CO2排出量可視化チャレンジの成果報告会を、新たに開設された共育共創コモンズで開催しました。この取り組みは、岡山県商工会連合会及び中国銀行との共催によるもので、約60名の地域の中小企業や支援機関関係者が参加しました。
取り組みの背後にある背景
岡山大学では、環境への配慮が高まる中、学生たちがカーボンフットプリント(CFP)算定に挑戦しています。これは、製品やサービスに関連する全ての温室効果ガス(GHG)の排出量を可視化し、持続可能な経営を支援するための重要な方法です。特に、サプライチェーン全体で温室効果ガスの排出削減を進める必要性が叫ばれています。
報告会の冒頭で、環境省の峯岸律子課長補佐が参加し、「岡山大学の取り組みは特にモデル性が高い」と称賛されました。大学が今後も地域の脱炭素経営を推進し続けることへの期待が寄せられています。
学生によるCFPチャレンジ
今回のチャレンジは、天王寺谷達将准教授の研究室に所属する学生によって実施されました。岡山技研工業株式会社が製造する2種類の製品について、経済産業省や環境省が定めたガイドラインに基づいたカーボンフットプリントの算定に挑戦し、参加した学生たちは、実際のデータを用いて分析を行ったのです。
参加した学生たちは、管理会計や原価計算の知識が環境問題に応用できることに驚き、CFPが消費者にとっても環境に配慮した選択を可能にする重要な指標であることを実感しました。今後の就職活動でも、この経験を活かしたいと意気込んでいます。
地域との連携と成果
岡山技研工業の川上哲治専務取締役も参加し、学生たちとの学びを通じてCFPの重要性を理解することができたとコメント。特に、原材料の輸送方法や積載率がCO2排出量に与える影響を学び、今後の企業価値向上に向けた取り組みに積極的に関与する意向を示しました。
このように、岡山大学では地域の中小企業との協力を強化しながら、有意義な取り組みを進めています。来年度も県内の支援機関と連携し、同様のチャレンジを行う計画が進められています。学内では、環境省事業への応募や、産学官の連携による地域の脱炭素化支援に支障のないように進めていくことが目指されています。
期待される未来
地域の持続可能性を高めるため、岡山大学は引き続き革新的な取り組みを進め、地域社会のカーボンニュートラルへの取り組みを広げる意向です。このような活動によって、岡山大学は地域社会における環境問題の解決に貢献し、未来の持続可能な社会の構築に寄与していくことが期待されています。
岡山大学の目指す「地域中核・特色ある研究大学」としての役割が今後も注目されます。
参考リンク
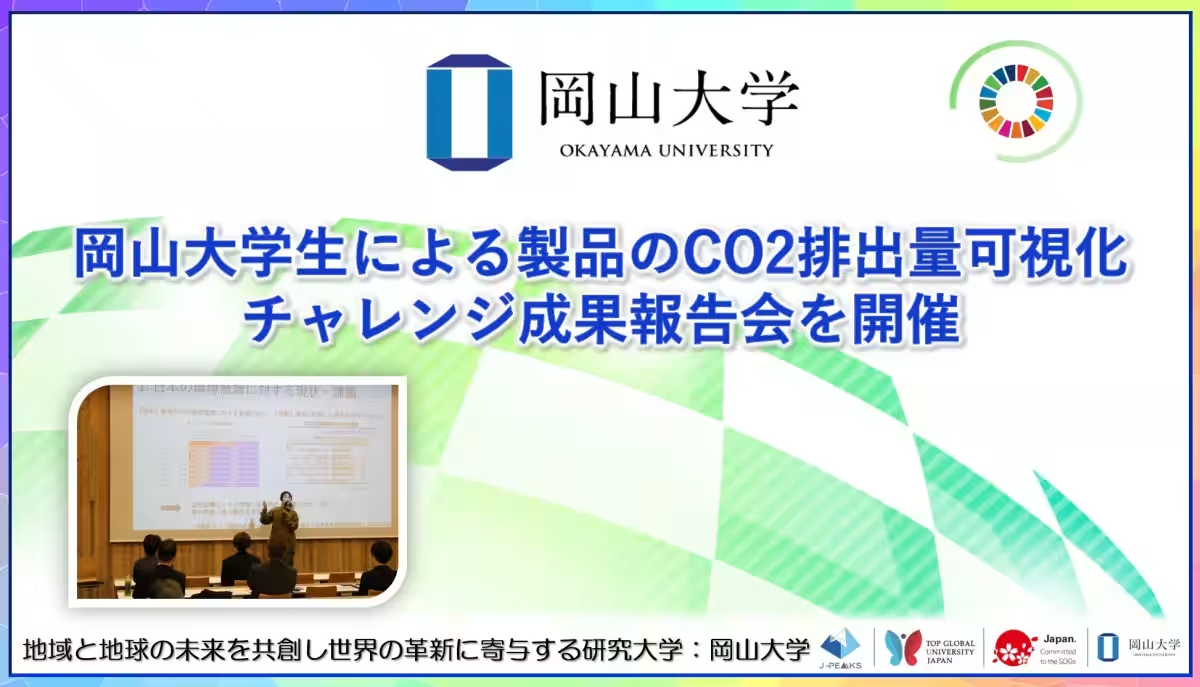









会社情報
- 会社名
- 国立大学法人岡山大学
- 住所
- 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス本部棟
- 電話番号
- 086-252-1111
トピックス(地域情報)
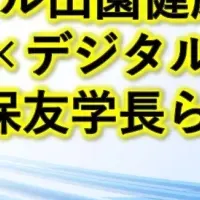
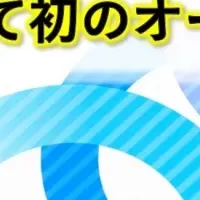
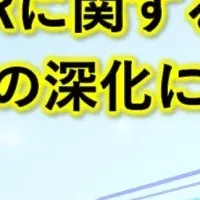
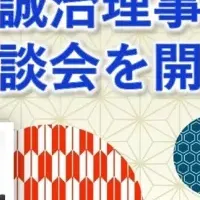
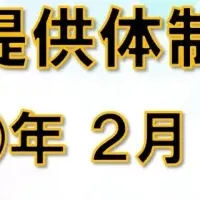
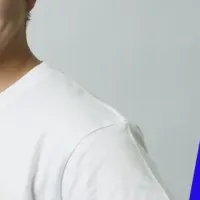




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。