
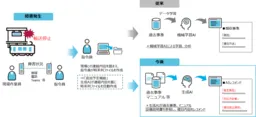
BIPROGYがJR東日本向けに生成AIの復旧支援システムを導入
BIPROGYが提供する新たな復旧支援システム
BIPROGYは、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)に対し、生成AIを駆使した復旧支援システムを提供開始しました。本システムは、鉄道の通信設備に特化したもので、故障時の情報を時系列で入力することで、AIが過去の類似事例を素早く抽出し、的確な故障原因や復旧作業を提案します。この技術により、迅速な復旧が可能となり、指令員の作業負担も軽減されることを目指しています。
背景と必要性
少子高齢化や人口減少が進む日本では、鉄道利用者のみならず、鉄道事業者の従業員も今後大きく減少することが予想されています。そのため、限られた人員で運営される鉄道オペレーションの効率化が求められています。JR東日本は、グループ経営ビジョン「変革2027」を掲げ、デジタル技術を用いた業務の変革を進めています。2024年10月に発表された「鉄道版生成AI」の開発も、その一環です。
BIPROGYは、これまでに培ったデジタル技術を駆使し、鉄道設備の保全業務の省力化に貢献してきました。遠隔モニタリングや踏切の遠隔監視など、多岐にわたるプロジェクトを推進しています。
システムの概要
新たに導入された復旧支援システムは、設備故障時に時系列情報を入力することにより生成AIがリアルタイムで過去の事例を分析し、故障原因や復旧作業の提案を行います。従来の方法では、指令員がマニュアルに従って原因を特定する作業が長引くことがありました。このシステムの導入によって、運転再開までの時間を大幅に短縮し、業務負担の軽減と復旧指示の品質の安定化が期待されます。
特徴
本システムには以下のような特徴があります。
1. 適用範囲の拡大
従来の機械学習では、導入場所ごとに膨大なデータ収集が必要でしたが、生成AIを活用することで、迅速かつ低コストで適用範囲を広げることが可能になります。
2. 復旧作業の迅速化
過去の復旧情報やマニュアルを参照し、迅速な復旧手続きの提案を行い、故障原因を解析します。また、新機能として、指令所と現場の無線通信内容の文字化や要約機能も開発中で、2025年度に導入予定です。
未来の展望
今後、BIPROGYは鉄道設備保全分野における知見をもとに、クラウド型の映像監視サービス「スマートユニサイト for Railway」や「踏切メモリ遠隔監視サービス」を活用し、さらなるサービスの創出を目指します。これらのサービスによって、鉄道事業者の輸送品質の向上に寄与することを目指しています。
まとめ
BIPROGYの復旧支援システムは、JR東日本の鉄道運営の効率化と安全性向上に向けた重要な一歩です。生成AIの導入による業務の自動化は、将来の鉄道オペレーションの在り方を大きく変える可能性を秘めています。
このシステムが実用化されることで、鉄道業界の持続可能性と、安全運行の確保に向けた挑戦がさらに加速することを期待しています。
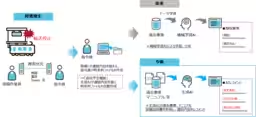
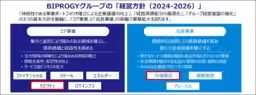
会社情報
- 会社名
- BIPROGY
- 住所
- 電話番号
トピックス(IT)




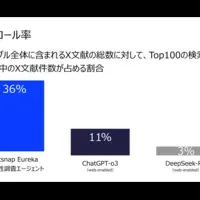
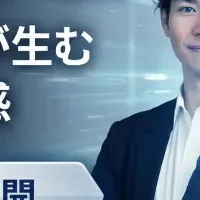
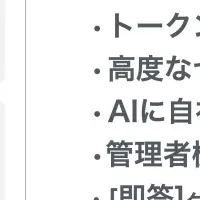

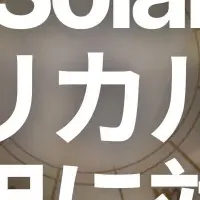
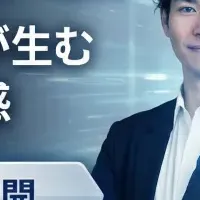
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。