

京都市、循環経済の未来を拓くフォーラムが開催される
京都市、循環経済の未来を拓くフォーラムが開催される
2024年1月16日、公益財団法人京都市環境保全活動推進協会と一般社団法人Impact Hub Kyotoは共催で「サーキュラーエコノミーに向けての実践とエコシステム構築」というフォーラムを開催しました。このイベントは、環境保全に力を入れる京都市において、循環型社会の形成に寄与する重要な機会となりました。
フォーラムの内容と意義
イベントの中で、京都市の持続可能な社会の形成に向けた取り組みや、システム思考に基づくリテラシーについての講演が行われました。特に、実践者の活動を支援するための具体的なアプローチを議論するワークショップも、フォーラムの大きな見どころでした。
Impact Hub Kyotoは、この1年間、サーキュラーエコノミーの啓蒙活動や支援ツールの開発に力を入れてきました。その成果として、このフォーラムは、京の地域特性を生かしたサーキュラーエコノミーのあり方を模索し、地域経済や環境負担の軽減に貢献することを目指しています。
京都の特色を生かし、実践者たちの事業を支援することで、経済的・環境的なコスト削減が期待されています。また、地域のレジリエンスを高めることが、持続的な社会の構築に向けた鍵となるという認識が深まりました。
フォーラムの具体的な進行内容
開催を報告する中、以下のようなプログラムが実施されました。
1. オープニングトーク(15時~15時10分)
フォーラムの趣旨や意義についての紹介が行われました。
2. 講演セッション(15時10分~16時10分)
「京都の環境保全の歩みから学ぶ — サーキュラーエコノミーへの布石」と題し、京都市がこれまで取組んできた循環や環境保全の歴史についての振り返りがありました。特に、空き缶条例や気候変動対策などが如何に循環型社会形成への基盤となっているかが示されました。
講演者には、京都市環境保全活動推進協会の理事長である新川達郎氏や、京都市産業技術研究所の理事長・西本清一氏が参加しました。
3. ワークショップ前インプットトーク(16時10分~16時40分)
加藤敦氏による「サーキュラーエコノミーに向けた施策を生み出す戦略とロジックモデル」が解説され、参加者が具体的な行動に移すための知識が共有されました。
4. ワークショップ(16時40分~17時55分)
支援機関と実践者が共に考える場が設けられ、具体的な支援の手法が議論されました。多くの実践者が直面している課題に対し、相互理解を深めながら効果的な解決策を模索しました。ファシリテーターとして塩瀬隆之氏が務めました。
5. クロージングトーク(17時55分~18時)
フォーラムのまとめが行われ、参加者同士のネットワーキングの機会も提供されました。
6. 懇親会(18時~フリータイム)
参加者が自由に交流できる場が用意され、さらなる意見交換やアイデアの共有が行われました。
このフォーラムは、サーキュラーエコノミーの概念を日常のビジネスや活動にどう生かすかを考え、地域の持続可能な未来に向けた大きな一歩となるでしょう。京都市が育んできた伝統と革新の融合が、新たなエコシステムを形成するための鍵となることが期待されます。
ツールキットとImpact Hub Kyotoについて
さらに、Impact Hub Kyotoではサーキュラーエコノミーの概念を導入するためのツールキットを公開しており、大学や行政、支援機関が活用できる具体的な資料が整っています。これにより、サーキュラーエコノミーの普及促進やプロジェクトの成功に向けた基盤を支えています。
このように、京都市は循環型社会に向けてアクティブに活動を展開し、さらなる地域発展の道を模索しています。今回のフォーラムに参加した皆が、それぞれの立場での貢献を果たし、サステイナブルな未来の形成を推進することが期待されます。

会社情報
- 会社名
- 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会
- 住所
- 京都府京都市伏見区深草池ノ内町13京エコロジーセンター
- 電話番号
関連リンク
サードペディア百科事典: 京都府 京都市 サーキュラーエコノミー 京都市環境保全活動推進協会 Impact Hub Kyoto
トピックス(地域情報)

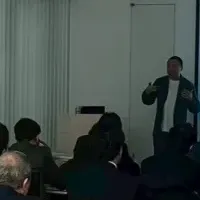
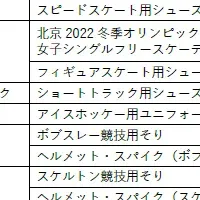



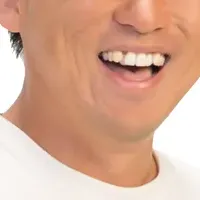



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。