
金融審議会がサステナビリティ情報保証の新たな枠組みを検討
サステナビリティ情報の保証に関する議論がスタート
日本では、金融審議会が「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」を設置し、第1回会合を開催しました。この会合では、サステナビリティ情報の保証における新たな枠組みや、業務を実施する者が求められる要件について、専門家や企業の意見が交わされました。
新たな枠組みの重要性
近年、サステナビリティに関する情報開示は企業にとって重要な課題となっています。金融商品取引法においても、上場企業に対してサステナビリティ情報を開示する義務が求められており、投資判断における信用性の確保も重要です。この専門グループでは、一定の信頼性を担保するために、サステナビリティ保証業務の実施者に対して、公認会計士などと同等の要件を課すことが議論されました。
業務制限と責任の明確化
業務を行う際の制限や責任についても慎重に議論され、サステナビリティ情報の保証に必要な質を保つためには、適切な管理体制と責任が求められる考えが示されました。特に、セクターや業種によって仕様が異なるサステナビリティに関連した情報は、内容に応じた適切な保証基準の整備が必要とされています。これにより、情報の開示者が不必要なリスクを抱えることなく、実践可能な範囲での保証体制が構築されることが期待されています。
国際的な動向との整合性
欧州や米国でもサステナビリティ情報に対する保証の重要性が高まっており、特にCSRD(企業に対するサステナビリティ報告指令)に基づく動向が注目されています。こうした国際的な動向を考慮しつつ、日本国内における保証基準や実施要件の設計が進められています。国際的な品質管理基準(ISQM1)や倫理規範との整合を図ることで、日本のサステナビリティ保証業務においても適切な信頼性が確保される見込みです。
結論
サステナビリティ保証に関する専門グループでは、企業の競争力を保ちながら、どのように信頼性のある保証体制を構築するかが課題となっています。今後も、様々な意見を取り入れながら、実効性のある制度の検討が求められるでしょう。展望としては、企業の負担を軽減しつつ、高品質の証明を維持するための持続可能な枠組みの構築が進められていくことが期待されます。
トピックス(経済)



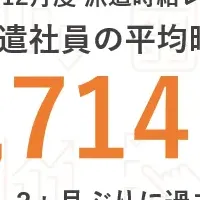
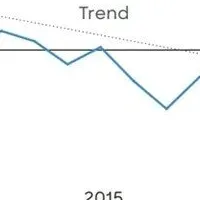





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。