

梅の収穫量が歴史的に減少し価格が急騰、背景には不作の要因が
梅の不作による歴史的な価格高騰
近年、梅の収穫量が大幅に減少し、価格が急騰する事態が発生しています。全国のスーパーマーケットで「農家の直売所」を運営する株式会社農業総合研究所が、2023年5月から6月の梅の販売動向を調査した結果、この異常事態の詳細が浮き彫りになりました。具体的には、5月の収穫量は昨年の56%、6月は66%と、前年比で半減近くに達しています。これに伴い、梅の価格も高騰し、5月は前年の644円から746円、6月は646円から907円と、いずれも115%を超える上昇を見せています。
不作の主な原因
梅の不作にはいくつかの要因が複合的に影響しています。最も顕著な原因の一つは、暖冬による受粉困難です。和歌山県の代表的な品種である南高梅は自家受粉ができず、他の品種からの花粉を頼りに実をつけますが、暖冬の影響で開花時期がずれ、その結果受粉がうまくいかなかったことが収穫量減少の主因となりました。
また、暖冬は害虫の増加にも寄与しています。通常、この時期に寒さにさらされることで減少するはずのカメムシが、気温の上昇で増殖し、梅の木にダメージを与えています。特に今年は、カメムシ以外の害虫も生き残りやすい環境のため、梅の木に対する影響がさらに深刻化しています。
さらに、3月に降った雹も大きな打撃を与えました。日本一の梅の産地である和歌山では、雹によって多くの梅が傷つき、販売可能なものが著しく減少しました。これらの要因が相まって、梅の供給量が減ったことは明らかです。
現在の市場状況
梅干しについては、現在の価格は昨年と大きな差は見られません。梅干しは1年をかけて製造されるため、収穫数の減少が直ちに価格に反映されるわけではありません。ただし、年末に向けて今年の収穫が梅干しに使われるようになると、価格が上昇する可能性が考えられます。
調査の方法
この販売動向の調査は、2023年5月から7月にわたって行われました。全国のスーパーマーケットにおける2,000店舗以上の「農家の直売所」から販売データを集計し、生産者へのヒアリングに基づいています。調査に協力したのは株式会社松川農園で、同社は和歌山県みなべ町の南高梅をおすすめしています。
会社情報
株式会社農業総合研究所は、「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」をビジョンに掲げ、全国の約10,000名の生産者と約2,000店舗の小売店を結ぶプラットフォームを構築しています。和歌山県和歌山市に本社を置き、産直流通のリーディングカンパニーとして活動しています。
詳細な商品情報や会社情報は以下のリンクから確認できます。






会社情報
- 会社名
- 株式会社農業総合研究所
- 住所
- 和歌山県和歌山市黒田99-12寺本ビルII4階
- 電話番号
- 073-497-7077
トピックス(地域情報)


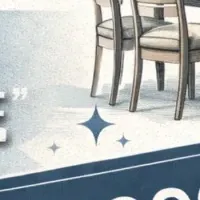




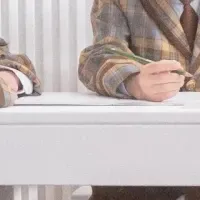


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。