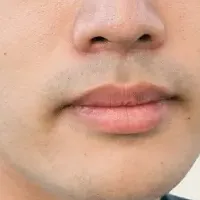

日本マーケティング協会が34年ぶりに新たなマーケティング定義を策定
日本マーケティング協会が新しい定義を制定
公益社団法人日本マーケティング協会は、1990年に制定されたマーケティングの定義を34年ぶりに見直しました。これまでの定義を刷新する理由は、急速に進化するデジタル技術や顧客関係の変化に対応する必要性からです。
背景
近年、AI、IoT、ビッグデータなどのデジタル技術が急速に普及し、DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じたマーケティング施策が企業の戦略にとって不可欠になっています。それにより、データの蓄積と顧客分析の精度が顕著に向上しています。一方で、シェアリングエコノミーやクラウドファンディングといった新しいビジネスモデルも登場し、企業と顧客の関係性がますます重要視されるようになりました。
また、2030年に向けたSDGsへの取り組みが企業に求められる中で、持続可能性を意識したビジネスを展開することが必要です。これらの要因が、マーケティングの役割を変化させる契機となっています。
新たな定義の制作過程
新しいマーケティングの定義は、昨年の理事長交代を契機に発足した委員会によって検討されました。委員会では、国内外のマーケティング定義の調査や、日本の社会に特有の視点を取り入れるための議論が行われました。議論を通じて、「価値共創」「ステークホルダーとの関係構築」「社会への貢献」といった言葉が重要なキーワードとして浮かび上がりました。
このプロセスを経て、2024年制定の新しい定義が決定されました。新定義は、企業だけでなく、個人や非営利団体をも対象とし、顧客や社会と共に価値を創造し、より豊かで持続可能な社会を実現するための基本となります。
新しいマーケティングの定義
新たに策定されたマーケティングの定義は以下の通りです。
マーケティングとは、顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。
この定義は、企業、個人、非営利組織にとっての共通の目標を示し、戦略や活動の見直しを促します。
制定委員会の構成
マーケティング定義の制作を担った委員会は、理事長の恩藏直人教授をはじめ、様々な業界や学問の専門家が集まりました。計11名で構成され、その多様な視点から議論が重ねられました。
まとめ
この新しい定義の策定は、マーケティングの未来を見据えた重要な一歩です。デジタル技術の進化や社会の変化に対応しながら、企業と顧客の新たな関係性を築くことを目指しています。今後、マーケティングは持続可能性や価値共創にますます重きを置くことでしょう。これからも日本マーケティング協会の取り組みに注目していきたいと思います。
会社情報
- 会社名
- 公益社団法人日本マーケティング協会
- 住所
- 東京都港区六本木3-5-27六本木山田ビル9階
- 電話番号
- 03-5575-2101
関連リンク
サードペディア百科事典: 東京都 港区 マーケティング デジタルトランスフォーメーション 日本マーケティング協会
Wiki3: 東京都 港区 マーケティング デジタルトランスフォーメーション 日本マーケティング協会
トピックス(経済)
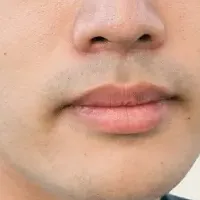


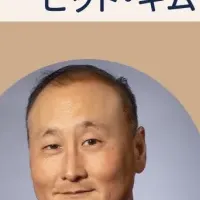


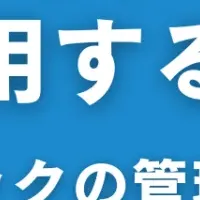



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。