

WHILL社と吉備国際大学が目指す多様な地域社会の実現と持続可能な未来
WHILL社と吉備国際大学の魅力的な連携
WHILL株式会社と吉備国際大学が、より多様で住みやすい地域社会を実現するための産学連携を始めることを発表しました。この取り組みは、すべての人にとってアクセシブルな未来の地域社会を共に考え、具体的な施策の実行を目指しています。
産学連携の背景
人口の高齢化や過疎化が進む中で、地域社会における「移動」の重要性はますます高まっています。特に、近距離での移動を支えるモビリティサービスが求められています。WHILL社は2012年の創業以来、利用者が日常的に「ウィル」を使える環境を整備してきました。このたびの連携は、双方が持つ専門知識や技術を持ち寄り、より良い社会を作るための一歩となります。
具体的な施策の内容
連携の第一弾として、吉備国際大学のキャンパス内で「ウィル」の自由な利用を促進する「フリーウィル」プログラムを導入します。学生たちはこのモビリティを通じて、介護福祉や観光、まちづくりといった多様な分野の学びに直結させることが期待されています。特に、看護学や理学療法を学ぶ学生たちは「ウィル」を生活の質向上の道具として捉え、外出支援に有効活用する方法を探ることが可能です。
一方、経営社会学科の学生は、従来の「電動車椅子」というイメージから脱却し、「近距離モビリティ」としての利点を広める方法について考察します。このような各分野での視点は、ウィルの普及をより効果的にする鍵として機能します。
フィールドワークと未来の町の体験
さらに、2025年2月12日には、吉備国際大学の学生が「ウィル」を利用して紺屋川地区を散策するイベントを計画しています。この実際の体験を通じて、参加者は誰もが簡単にインクルーシブな地域を移動できる状況を疑似体験し、五感を使って地域の魅力を再発見します。
この取り組みは、単なる学びだけでなく、地域の活性化にもつながることを目指しています。観光資源としての地域の価値や、住民の生活の質を下支えする手段としての「ウィル」の可能性を実感させるでしょう。
今後の展望
WHILL社は、地域との密な連携を図り、今後も多様な活動を通じて近距離モビリティの普及に努めていく考えです。国土交通省の推進するウォーカブルなまちづくりの重要性も踏まえ、地域のさまざまなステークホルダーと協力し、お互いにとって意義のあるイニシアチブを展開します。
具体的には、観光業界との連携や、地域の居住環境の改善に寄与する施策を打ち出していく予定です。
結論
WHILL社と吉備国際大学の連携は、単に移動手段を提供するだけでなく、地域全体の活性化を目指しています。すべての人にとってアクセスしやすい地域社会を構築するために、両者の知識や経験を活かした取り組みが今後も期待されます。このような挑戦が地域未来の礎となることを願っています。





会社情報
- 会社名
- WHILL Inc
- 住所
- 東京都品川区東品川2丁目1-11 ハーバープレミアムビル 2F
- 電話番号
- 080-0800-4338
トピックス(地域情報)


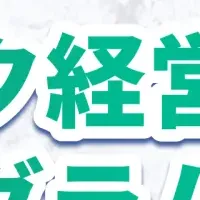







【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。