
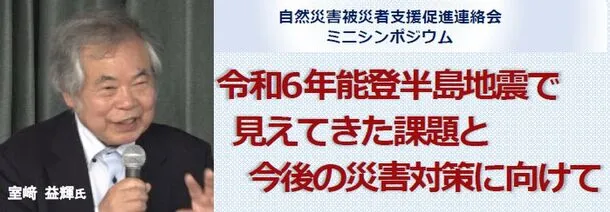
令和6年能登半島地震の復興に向けた取り組みと課題
令和6年能登半島地震の復興に向けた取り組みと課題
2024年6月に開催された「令和6年能登半島地震で見えてきた課題と今後の災害対策に向けて」というミニシンポジウムでは、専門家や活動家が能登半島地震の現状と今後の支援方針について討議しました。このシンポジウムは、「自然災害被災者支援促進連絡会」が主催し、オンラインも併用で行われました。参加者は阪神淡路大震災をはじめとする歴史的な災害への経験を基に、被災者支援の新たな方法論を模索しました。
シンポジウムの概要
シンポジウムでは、基調講演を神戸大学名誉教授の室崎益輝氏が行い、能登半島地震の影響を受けた地域の復興に向けた具体的な提言を強調しました。室崎教授は、地震による被害が地域社会に与えた影響を分析し、生活再建に向けた制度の改善の重要性を訴えました。特に、災害後の対応策として、「被災者生活再建支援法」の見直しが求められています。
次に、弁護士の津久井進氏が登壇し、法律的な視点から被災者支援の課題を指摘しました。津久井氏は、生活の再建を目的にした支援法が適用されることの重要性を語り、実際の被害実態を反映できるようなシステム作りが必要だと述べました。
被災者支援の視点
大阪公立大学の菅野拓准教授は、被災者支援の中心に「人」を置くべきだと強調しました。物質的な支援だけでなく、人間の生活や福祉に目を向けることが大切だとし、社会保障の観点から被災者支援が行われるべきだと語りました。災害時には、民間と行政が連携し、スムーズな支援を実現することが求められています。
さらに、一般社団法人社会的包摂サポートセンターの澤上幸子氏は、被災者の声を社会に届けることの重要性を訴えました。「よりそいホットライン」を通じて、被災者からの相談を受け付け、その思いや不安を可視化する活動に力を入れています。
復興のビジョン
復興に向けたビジョンがないと、再建は難しいという室崎教授の言葉は印象的です。「思いや夢のある『真』の創造的復興を」とのメッセージは、単なる物的再建に留まらず、コミュニティが一体となって未来へ向かう姿勢を重視しています。被災者自身が自立できるような支援制度の構築が求められる中、復興後の社会像を考えることは非常に重要です。
結論
令和6年能登半島地震によって浮き彫りになった課題を解決するためには、制度の見直しや多様な視点からの支援が不可欠です。シンポジウムでの提言を基に、地域に根差した支援が進むことが期待されています。被災者一人ひとりの声に耳を傾けることで、より効果的な支援の実現へ向けて努めていく必要があります。
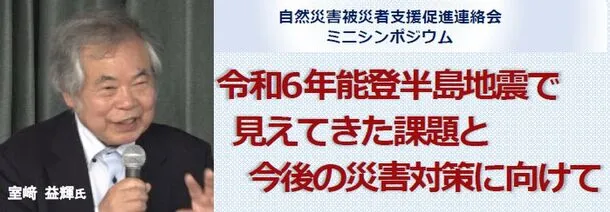
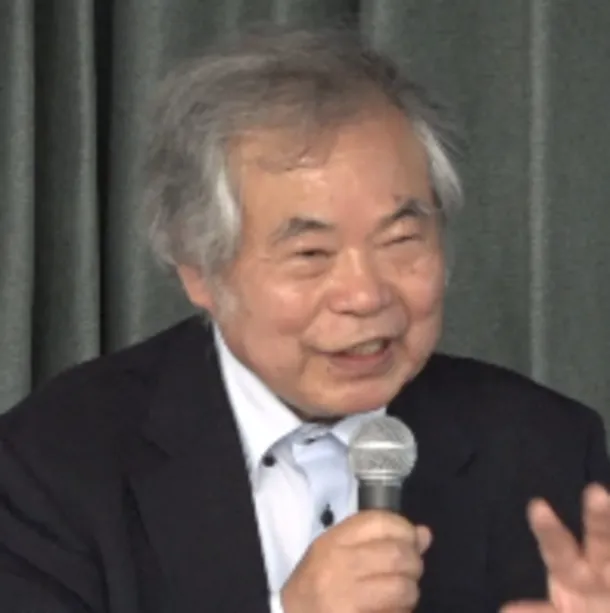
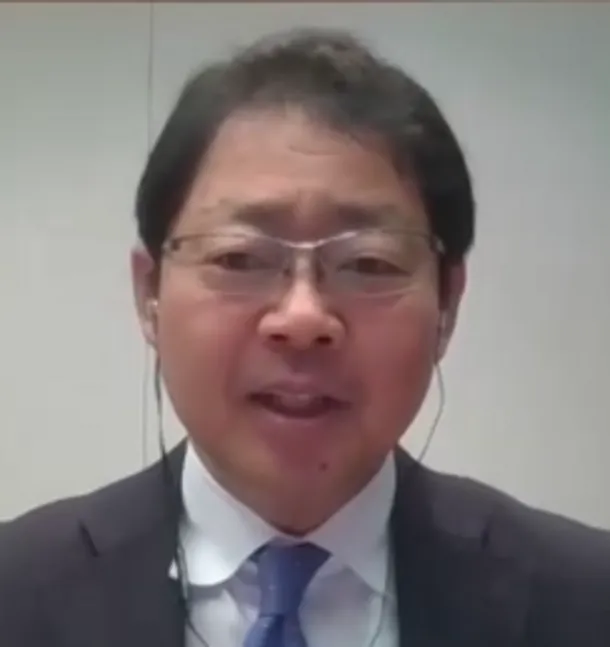
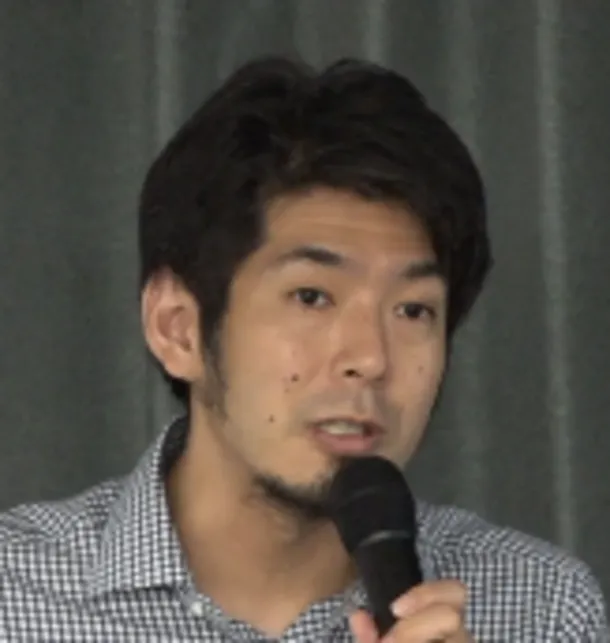
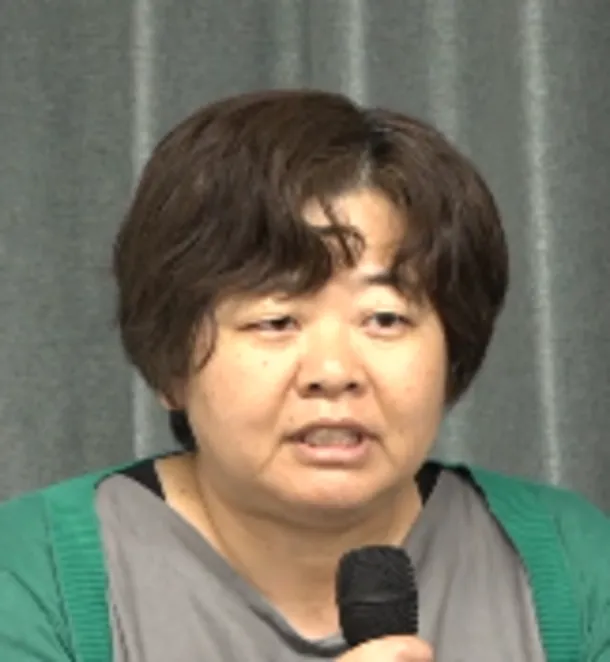
会社情報
- 会社名
- 自然災害被災者支援促進連絡会
- 住所
- 電話番号
トピックス(地域情報)

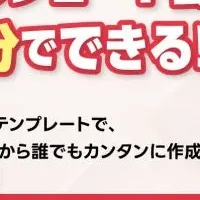



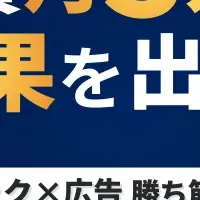




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。