

沖縄のテリハボクとポンガミアから新たなSAF原料が誕生
沖縄の新たなSAF原料の誕生
新しい時代の航空燃料として注目されている持続可能な航空燃料(SAF)が、沖縄の特殊な植物から生まれました。今話題となっているのは、食用とはならないテリハボクとポンガミアの二種の植物から、100%バイオマス由来のSAFを生成したというニュースです。これは、航空業界での二酸化炭素(CO2)排出量削減を目指す取り組みの一環であり、環境に優しい新たな資源の確保に向けた重要なステップとなります。
SAFとは何か
SAF(Sustainable Aviation Fuel)は、持続可能性を重視した航空燃料であり、再生可能な資源や廃棄物を原料として製造されます。これにより、従来の化石燃料と比較して温室効果ガス(GHG)排出量を大幅に減少させることが可能です。特に、日本では2030年までにジェット燃料使用量の10%をSAFに切り替える計画がありますが、現在の研究と実証がその未来を支える鍵となります。
新たな原料の生成
今回の成果は、株式会社J-オイルミルズが取り組んだNEDO事業の一環であり、沖縄県の街路樹から集めたテリハボクとポンガミアの種子から始まりました。これらの植物は、土地の条件を選ばず育つため、食料用農地との競合を避けられます。搾油や精製処理後、生成された油脂は水素化や異性化の工程を経て、最終的に国際品質基準「ASTM D7566 Annex A2」に適合する質の高いSAFとして完成しました。
なぜテリハボクとポンガミアなのか
テリハボクの種子はその高い脂肪分(40%〜50%)で知られ、ポンガミアも同様に栄養価の高い油分を持つことで評価されています。これらの植物は、農地としてはふさわしくない厳しい環境でも栽培可能です。これにより、今後のSAF供給網の拡大に貢献できると期待されています。
今後の展望
J-オイルミルズは、今回の事業を通じて新たなSAF原料の可能性を開拓しました。今後は燃料の品質を確保することに加えて、環境認証であるCORSIA適格燃料登録を目指します。また、石油精製業者との連携を図り、さらなる技術の進化に向けた取り組みを強化します。
1月29日から31日まで、東京ビッグサイトにおいて行われる「第19回再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム」でも、この革新的な取り組みが紹介される予定です。持続可能な未来に向け、私たちがどのように資源を利用し、環境問題に取り組むかが問われています。この成果は、次世代の航空燃料のサプライチェーン構築への一歩となり、未来の航空業界に新たな希望をもたらすことでしょう。
まとめ
沖縄県の特産物を利用した新しいSAF原料の開発は、環境問題の解決に向けた重要な一歩です。食用に適さない植物を資源化することで、安定したSAF供給の実現が期待されています。これからの航空燃料は、より持続可能な形で私たちを空へと運んでくれるでしょう。航空業界の未来が明るくなることを願います。

会社情報
- 会社名
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
- 住所
- 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番ミューザ川崎セントラルタワー
- 電話番号
- 044-520-5207
トピックス(経済)


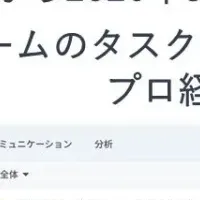




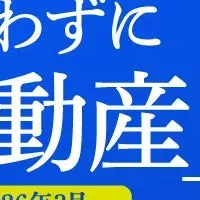


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。