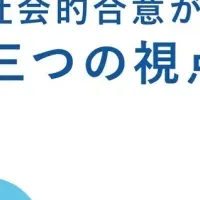
偽造キャッシュカードの被害急増、ネットバンキング注意喚起が必要な状況
偽造キャッシュカードやネットバンキングによる不正取引が急増中
近年、私たちの金融取引は急速にデジタル化していますが、それに伴い犯罪も巧妙化しています。特に、偽造キャッシュカードやインターネットバンキングを利用した不正取引が急増しています。これは、金融庁が発表した最新の報告書でも明らかにされています。
偽造キャッシュカード被害の現状
金融庁の報告によると、偽造キャッシュカードによる被害は、令和6年末までの期間で約7,684件に達しました。特に、これらの事件の大部分は、警察官などを装った犯人によるもので、被害者からキャッシュカードを騙し取る手口が目立っています。また、被害者が一瞬目を離した隙にキャッシュカードをすり替えられる場合もあります。
インターネットバンキングによる不正取引
インターネットバンキングによる預金の不正送金事件も深刻です。過去3年間で、件数は24,429件にのぼり、特にフィッシングサイトを利用した手口が増加しています。メールやSMSで届く偽のリンクから個人情報を盗む手法が一般化しており、注意が必要です。これにより、被害者は瞬時に自分の口座から資金を奪われる危険があります。
主な手口と注意点
金融庁は、このような不正送金犯罪の主な手口を公表し、注意喚起を行っています。以下のポイントに留意しましょう。
- - 不審なリンクに注意:メールやSNSで届くリンクをクリックする前に、必ず送信者を確認し、不審な点があれば無視するべきです。
- - 個人情報を意識:IDやパスワードは絶対に他人に教えないこと。自分で操作している時以外は特に注意を。
- - キャッシュカードの管理:キャッシュカードは常に自分の管理下におき、他人に渡さないようにしましょう。
被害に遭った場合の対処法
万が一、被害に遭ってしまった場合は、すぐに金融機関に連絡し、異常を報告しましょう。その後、警察にも相談することが重要です。また、金融機関による補償状況を確認し、適切な対応を求めることも忘れずに。金融機関では、すでに多くのケースで補償を行っている一方で、年々補償しないケースも増加しています。
まとめ
偽造キャッシュカードやインターネットバンキングの不正取引は、今後も成長が予測されるリスクです。金融庁の公表を参考にしつつ、個々が防止策を講じることが強く求められています。日常の意識を高めることが、被害を未然に防ぐ一歩となるでしょう。
トピックス(国内(政治・国会・社会・行政))
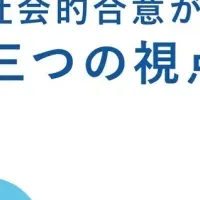


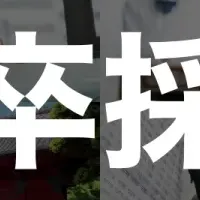
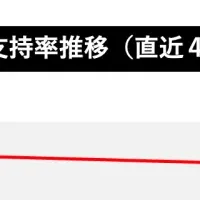





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。