

東京大学とポプラ社、絵本の影響に関する共同研究を発表
東京大学とポプラ社が共同研究を実施
東京大学CEDEP(センター)の研究チームとポプラ社は、2019年から共同研究を行ってきました。このプロジェクトは、現代のデジタルメディア普及時における幼児の絵本との関わりを探ることを目的としています。特に、スマートフォンやタブレットに触れる機会が増える中で、幼い子どもたちが本に接する機会が減少していることに危機感を抱いています。
研究成果の公開
この研究の成果は、2024年12月20日(金)に『発達心理学研究』第35巻第4号にて公表される予定です。研究の主要な著者は、東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センターの大久保圭介特任助教(現:国士舘大学文学部講師)、佐藤賢輔特任助教、浜名真以特任助教、野澤祥子准教授からなる4名です。
論文タイトルは『絵本の読み聞かせと幼児のかな文字識字および情動理解の関連:読み聞かせの質・量・開始時期に注目して』となっており、絵本の読み聞かせが幼児のかな文字の読み能力や情動理解能力にどのように影響を与えるかを明らかにしています。
研究のポイント
1. 読み聞かせの影響
オンライン調査を通じて、3〜6歳の幼児とその保護者を対象に、家庭における絵本の読み聞かせの量が子どものかな文字能力に、質が他者の情動理解能力に関連していることが示されました。これは、日本の幼児を対象とした初めての定量的な研究です。
2. 開始時期との関係
興味深いことに、読み聞かせを開始する時期は、子どもの識字能力や情動理解能力には直接的な関連がないことが分かりました。これは、どのタイミングで読み聞かせを始めるかよりも、その質や量がより重要であることを示唆しています。
3. 実践への影響
この研究は、家庭や保育施設における絵本を用いた教育活動の改善につながることが期待されています。具体的には、絵本をどう使うかについての指針が得られることでしょう。
研究の背景
最近のデジタル化が進む中で、子どもたちの読書環境が大きく変化しています。このような背景から、ポプラ社は「ひとりでも多くの子どもたちを本好きにしたい」という理念の下、東京大学CEDEPとの共同研究を始めました。研究を通じて、絵本の持つ固有の価値や、成果を育成するための新たな環境整備を目指しています。
エコシステムとしての研究
本プロジェクトでは、子どもを取り巻く絵本や本の環境をエコシステムとして捉え、家庭、保育園、地域社会それぞれの相互関係を探っています。発達心理学者U.ブロンフェンブレナーの理論を参考にし、子どもの発達が環境との相互作用から成り立つことを考慮しています。
さらなる情報
詳しい内容については、次のウェブサイトをご覧ください。
今後もこの研究から新たな知見が得られることが期待され、子どもたちの健やかな成長を支えるための資料として活用されるでしょう。

会社情報
- 会社名
- 株式会社ポプラ社
- 住所
- 東京都品川区西五反田3丁目5番8号JR目黒MARCビル12階
- 電話番号
- 03-5877-8101
トピックス(その他)


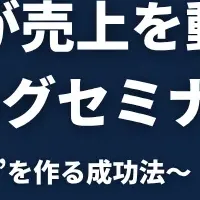

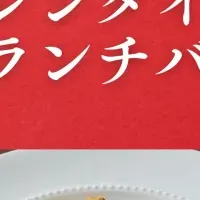
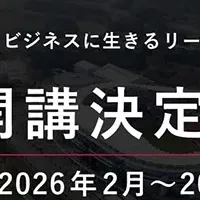



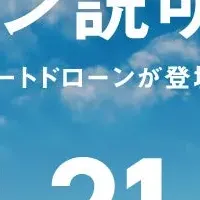
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。