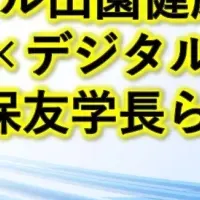

薬局薬剤師によるポリファーマシー解消の新しい取り組みと研究成果
薬局薬剤師によるポリファーマシー解消の最新研究
近年、高齢者の薬物治療における「ポリファーマシー」の問題が広く認識されるようになり、それに対応する取り組みが進められています。特に、株式会社カケハシは、薬剤師によるポリファーマシーへの介入に関する調査を行い、実際のデータをもとにした研究成果を発表しました。本記事では、この取り組みの概要、得られた成果、さらなる展望について解説します。
1. 背景と目的
この研究は、カケハシが開発した薬局向けサービス「Musubi」を通じて、国内の多くの薬局との連携によって蓄積した実データを基にしています。特に、65歳以上の高齢者を対象にしたポリファーマシー解消の重要性に焦点を当て、患者フォローや処方の実態を明らかにすることを目的としています。国も平成30年と令和2年において、薬局薬剤師の積極的関与を促す制度改正を行っており、この研究はそれに関連する重要なデータを提供するものです。
2. 研究概要
される調査は、2020年4月から2023年9月にかけて実施され、対象となる薬局は2,069ヵ所、65歳以上の患者は1,458,323人に及びました。調査方法としては、患者の年齢層ごとの服用薬剤数の分析や、支援料1・2の算定有無に影響を与える要因を探るために、一般化線形混合モデルが使用されました。この研究で得られたデータは、薬局薬剤師がポリファーマシーの解消に向けた具体的な行動を起こすための道しるべとなるものです。
3. 主な調査結果
調査の結果、65歳〜69歳の高齢者の中で6剤以上の薬剤を服用している割合は13%であるのに対し、85歳〜89歳では29.8%に達し、著しい開きが見られました。また、「ハイパーポリファーマシー」と言われる10剤以上を服用する患者は、最も若い年齢層でも1.9%なのに対し、90歳以上では7.3%と高い水準であることが判明しました。このことから、年齢が進むに従ってポリファーマシーのリスクが増加することが示されました。
さらに、調査期間中に支援料1を算定した薬局はわずか10.3%であることも明らかになりました。この結果は、ポリファーマシーの解消に向けたさらなる支援が必要であることを示唆しています。支援料1を算定した際に減薬対象となった薬剤のトップは消化性潰瘍用剤であり、続いてアレルギー薬や解熱鎮痛消炎剤が続くという興味深いデータも得られています。
4. 今後の展望
ここで収集されたデータと解析結果は、今後の医療現場での薬剤の適正使用に向けた貴重な情報となります。研究は、かかりつけ薬剤師の推進がポリファーマシー解消に寄与する可能性があることを示しており、薬剤師が積極的に減薬を提案する際の参考材料にもなるでしょう。
カケハシは引き続き、実臨床データの解明や薬剤の適正使用を推進し、患者にとってより良い医療サービスの確立を目指します。全ての医療従事者と患者がともに恩恵を受けられるような環境を整える努力を続けていきます。
会社情報
株式会社カケハシは、日本の医療システムの革新を目指し、ヘルステックスタートアップとして成長を続けています。テクノロジーを活用し、薬局体験アシスタント「Musubi」をはじめとしたプロダクトを展開。国内の薬局約12,000店舗をサポートし、医療業界全体の発展に寄与しています。
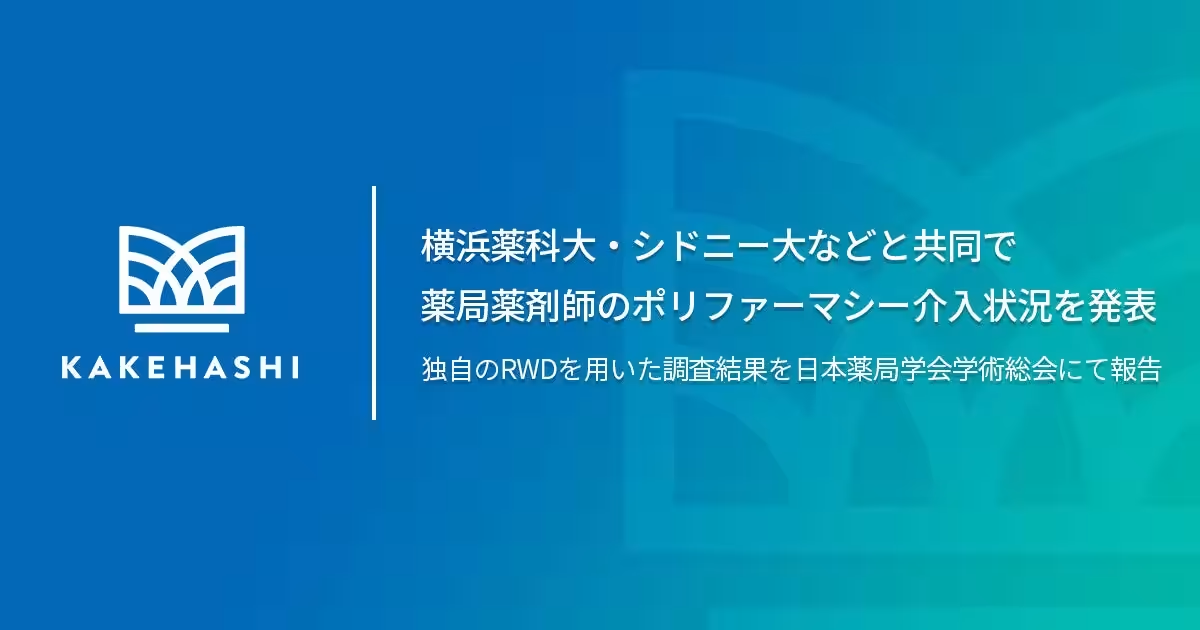
会社情報
- 会社名
- 株式会社カケハシ
- 住所
- 東京都港区西新橋二丁目8番6号住友不動産日比谷ビル5階
- 電話番号
- 03-6825-2058
トピックス(地域情報)
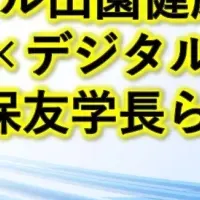
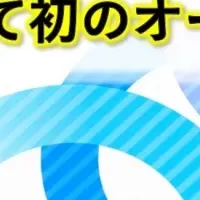
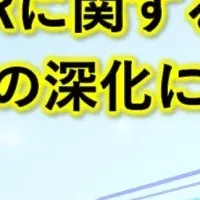
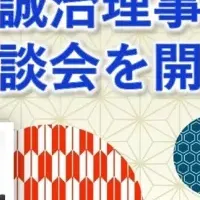
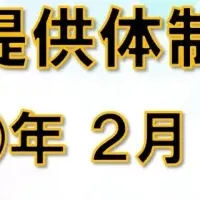
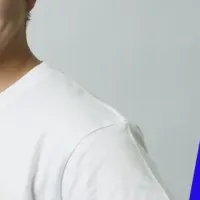




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。