
三菱総合研究所と東京大学が発表した持続可能な燃料の新たな研究成果
三菱総合研究所と東京大学の共同研究
三菱総合研究所(MRI)は、東京大学と協力し、「持続可能な燃料」についての詳細なレポートを発表しました。この取り組みは、脱炭素社会に向けたエネルギーの需給管理を目指す重要なステップです。
背景
2021年11月、日本企業の有志が集まり、東京大学内に設立されたプラットフォーム、ETI-CGC(Energy Transition Initiative – Center for Global Commons)は日本の脱炭素に向けた議論と実行を進めています。このイニシアティブに、MRIも2023年から参加し、ネットゼロの達成に向けた議論と分析を展開してきました。ETI-CGCの活動は、持続可能なエネルギーの普及を支える基盤となっており、各方面での支援が期待されています。
研究成果の概要
今回のレポートでは、水素、合成燃料、バイオ燃料などを「持続可能な燃料」として取り上げ、特に運輸分野に着目しました。MRIは独自に開発したエネルギー需給モデル「MRI-TIMES」を利用して、これらの燃料がどのようにエネルギー需給に寄与するのかを分析しました。
分析結果のポイント
1. 相互補完的な役割: 移動体セクターの管理において、持続可能な燃料の利用と電動化は互いに補完し合う重要な要素であることが示されました。
2. サプライチェーン構築の重要性: エネルギーの安定供給のためには、持続可能な燃料のサプライチェーンの確立が欠かせません。
3. 社会費用の低減効果: 持続可能な燃料の利活用は、社会全体のコスト削減に寄与する可能性があることが明らかになりました。
この分析を受けて、レポートでは持続可能な燃料の普及に向けた具体的な提言がなされています。特に、次の三つが重要視されています。
- - 国内利用環境の整備: 持続可能な燃料を利用しやすい環境を整えること。
- - 戦略的パートナーシップの構築: 政府や企業、学術機関との連携を強化すること。
- - 国際的な枠組みの構築: グローバルに炭素循環を促進するための国際連携を積極的に進めること。
今後の展望
MRIはこれまでも、日本におけるリアルなネットゼロ実現に向けた政策提言に尽力してきました。今回の東大CGCとの共同研究を契機に、さらなるステークホルダーとの連携を図り、社会的にも意義のある研究や提言を進めることを目指しています。
持続可能なエネルギーの利用は、私たちの未来にとって不可欠であり、今後の政策や技術の開発においても重要なテーマとなっていくでしょう。今回のレポートは、その道筋を示す貴重な指針となるでしょう。
会社情報
- 会社名
- 株式会社三菱総合研究所
- 住所
- 東京都千代田区永田町2-10-3
- 電話番号
- 03-5157-2111
トピックス(科学)

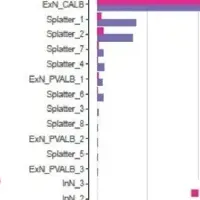

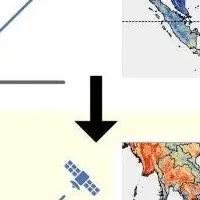
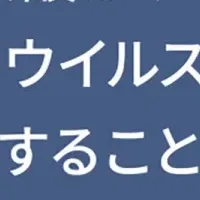




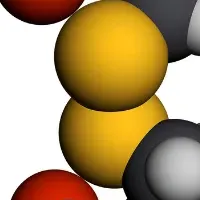
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。