

宮大工の技を未来へと繋ぐ!「こども宮大工プロジェクト」始動
宮大工の技を未来へと繋ぐ!
日本の美しい文化を支える職人、宮大工。その技術を次世代に継承するためにNPO法人「宮大工木造技術継承協会」が設立され、特に注目されるのが新たに開始された「こども宮大工1000人プロジェクト」です。このプロジェクトは、伝統技術を子どもたちに伝え、未来の宮大工を育てる試みとして、多くの期待が寄せられています。
宮大工とは?
宮大工は、日本の神社や仏閣の建設や修繕を手がける職人です。釘を使わず、木材で巧みに組み上げる「木組み」を用いたその技術は、古くから受け継がれており、地域の社寺の維持に欠かせない存在です。彼らの仕事は、世界遺産や国宝、地域に根ざした文化財を手がけることから、その重要性は計り知れません。
特に、宮大工の技術は2020年にユネスコの無形文化遺産に登録され、「伝統建築工匠の技」としての評価を受けています。この技術は、木材や草、土などの自然素材を活かし、持続可能な建築を支えるものであり、古代から現代に至るまでの知恵を集結させたものです。
宮大工技術のSDGsへの貢献
宮大工の仕事は、実はSDGs(持続可能な開発目標)とも密接に関連しています。彼らは歴史的な建造物を補修し、木材の持続可能な利用を実現しています。その背景には、木の植栽や地域の森の維持への貢献があるため、宮大工は1000年以上前からサステナビリティを体現してきた職人だといえるでしょう。とはいえ、近年、若手の宮大工が減少し、高齢化が進む中、技術の継承が課題となっています。
「こども宮大工1000人プロジェクト」とは
こうした背景を受けて始まったのが、「こども宮大工1000人プロジェクト」です。このプロジェクトでは、現役の宮大工の指導のもと、子どもたちが実際に手を使って技を学び、体験する機会を提供します。プロジェクトの参加者は、伝統技術を実際に体験することで、宮大工の魅力を知り、未来の職人としての一歩を踏み出すことが期待されます。
さらに、2022年11月19日には神奈川県相模原市のアリオ橋本でキックオフイベントが行われ、子どもたちが宮大工の技を学ぶ貴重な機会が提供されます。このイベントでは、カンナ削りのデモンストレーションや大工道具の展示、写真ギャラリーなど、さまざまな体験が用意されているため、地域住民にも広く周知されることになるでしょう。
今後の取り組み
「宮大工木造技術継承協会」は、今後も宮大工の育成に注力し、地域に密着した活動を進めていく方針です。その目的は、宮大工の技術を地域に根ざした形で活用し、過去の文化を未来につなげることです。また、外国への普及活動にも力を入れ、伝統的な日本文化の魅力を発信していく考えです。
若手の宮大工を増やすために必要な技術の習得には時間がかかりますが、こうしたプロジェクトを通じて、未来の宮大工たちがその技を継承し、さらなる発展を遂げていくことが期待されています。この活動が、宮大工技術の復興と日本文化の持続的な発展に貢献することを願っています。
会社情報
- 会社名
- 特定非営利活動法人 宮大工木造技術継承協会
- 住所
- 神奈川県愛甲郡愛川町半原2814
- 電話番号
- 090-2243-7914
トピックス(その他)



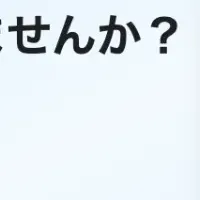

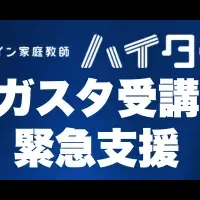
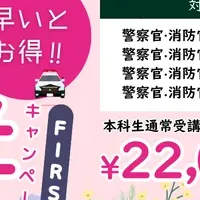
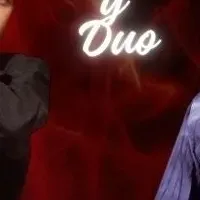


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。