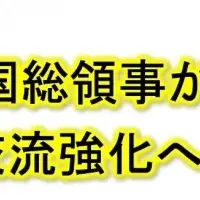
非常時に役立つマイナンバーカードの利用法とその実践例
非常時に役立つマイナンバーカードの利用法
近年、デジタル社会の進展が目覚ましく、私たちの日常生活においてデジタル技術の利便性が広がっています。特に、マイナンバーカードは、災害や緊急時においても幅広い利用シーンが増加しており、その重要性が高まっています。ここでは、非常時におけるマイナンバーカードの利点と具体的な利用法について詳しく見ていきましょう。
医療の現場での活用
非常時には、特に医療機関でマイナンバーカードが取り入れられています。たとえば、救急搬送が必要な状況で、患者が意識を失っている場合、医師や救急隊員は患者の医療情報にアクセスできず、適切な処置が遅れてしまうことがあります。そのような場面でも、マイナンバーカードを用いることで、救急隊員は患者の受診歴や服用している薬、アレルギー情報を迅速に取得でき、適切な医療を提供することが可能になります。これは「マイナ救急」として全国67の消防本部で実証実験が行われており、2025年度には全国展開が予定されています。
高額医療費の支払いの軽減
急な手術や入院が必要になった際、高額な医療費が発生する場合がありますが、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、患者が医療機関や薬局の窓口で一時的な自己負担をする必要がなくなります。高額療養費制度により、月内で支払う医療費が一定の上限額を超えた場合、その超過分が支給されるため、家計への負担が大幅に軽減されます。
避難時の情報共有
災害が発生した際、避難所で必要な医療を受けるためには、過去の診療履歴や薬剤履歴を医師と共有することが重要です。マイナポータルを通じて、避難所で医師と情報を共有することができるため、緊急な医療対応が迅速に行われます。これにより、避難者は安心して医療を受けることができます。
災害対応の支援
災害が発生した場合、マイナンバーカードは避難所入退出の管理や支援物資の配布に役立つことが期待されています。デジタル技術を用いた業務改善により、被災者情報を正確に把握し、適切な支援を行うための調査研究が進められています。これらの取り組みは、災害時の効率的な対応を助けるものであり、今後もさらなる実証実験や改良が行われるでしょう。
復旧時の手続き支援
復旧や復興の際、マイナポータルを通じて被災者支援のための各種手続きを行うことができます。たとえば、罹災証明書の発行や仮設住宅の提供、支援金の申請など、多くの手続きがオンラインで完結できるようになっています。これにより、役所に足を運ぶことなく、素早く手続きを進めることが可能です。
まとめ
マイナンバーカードは、非常時において非常に多くの場面で活躍するツールとしての可能性を秘めています。医療や避難所での利便性向上、さらに災害対応の支援業務の円滑化にも寄与することが期待されます。今後も、デジタル庁の取り組みにより、マイナンバーカードの利活用が進み、多くの人々の生活を支える存在となるでしょう。
トピックス(地域情報)
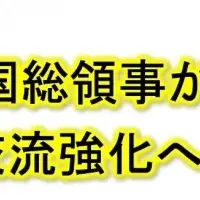
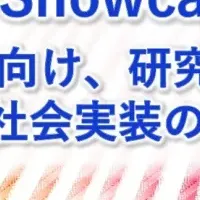

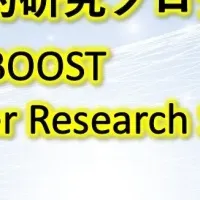
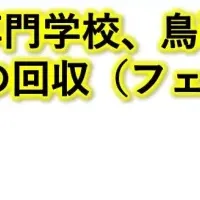
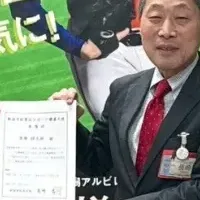

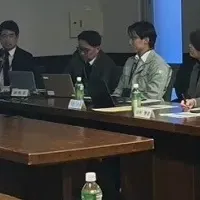
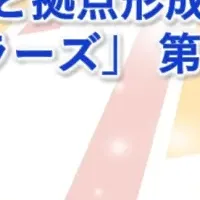
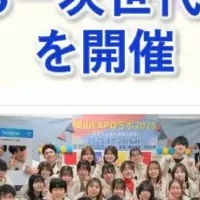
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。