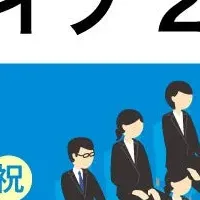
IBMの調査が示す、日本におけるサステナビリティーへのIT投資の現状と課題
IBMが発表したサステナビリティー調査の結果
日本IBMは、経営幹部を対象としたサステナビリティーに関する調査「The State of Sustainability Readiness Report 2024」の日本語版を公開しました。この調査は、循環型経済や環境への配慮が求められる現代において、企業がどのようにサステナビリティーに取り組んでいるかを掘り下げています。調査結果によれば、世界の経営幹部の88%および日本の経営幹部の67%が、今後12か月でサステナビリティー向上のためのIT投資を増やす意向を示しています。また、半数以上がこの投資を成長の機会と捉えている一方で、AIの適用には依然として課題が残っていることも浮き彫りになっています。
認識のギャップとAIの可能性
特に注意が必要なのは、AIがサステナビリティーにどのように影響を与えるかという点です。経営幹部の約90%が、AIがサステナビリティー目標の達成にプラスの役割を果たすと考えているにもかかわらず、実際には約6割の組織がその導入に消極的な状況です。この背景には、財務プランニングの問題や予算の制約が関わっていると考えられます。中でも、サステナビリティーに向けたIT投資の48%が、通常の運営予算からではなく単発の予算で賄われているというデータが示されています。
AIの導入については、エネルギー使用量や運用効率の向上など、新たな取り組みが求められています。リーダーたちは、エネルギー効率の高いプロセッサーへの投資やオープンソースコミュニティとの協力を推進し、AIの環境フットプリントを削減する努力をしています。AIに適した人材の確保も課題として挙げられており、スキルを持った人材が不足している中で、適切な人材を見つけることは特に難しいとされています。
サステナビリティーの測定課題
組織がサステナビリティーを長期的に実現していくためには、どのようにその活動を測定するかが重要な課題です。調査では、世界の経営幹部が主に再生可能エネルギー消費量やリサイクル率をKPIとして重視していることが明らかになっていますが、実際にはこれらのデータが十分に成熟していないことも指摘されています。この状況は、報告プロセスの難しさを招いており、サステナビリティーKPIの測定は多くの組織の共通の課題となっています。
経営幹部と意思決定者の認識の差
調査の結果、経営幹部とその他の意思決定者の間にサステナビリティーに関する認識の差が明らかになりました。経営幹部は自社の気候変動レジリエンスに関して楽観的な見方をしているのに対し、バイス・プレジデントやディレクターはその意見にが名を潜めています。特に日本の経営幹部は、サステナビリティーの課題を非常に困難だと捉えている傾向が強く、これが戦略策定の妨げになっています。
組織に求められるアクション
IBMの調査結果は、組織におけるサステナビリティー向上のための具体的な戦略を提示しています。まず、組織に適したAIツールに投資することが推奨されています。生成AIは、二酸化炭素排出量の削減や持続可能なビジネスのシナリオ作成に寄与することが期待されています。
次に、データを活用して経営幹部とその他の意思決定者との間の認識の差を縮小する必要があります。データ分析ツールを使うことで、組織全体の可視性と整合性を高めることが可能です。最後に、メガワット時のエネルギー消費量やリサイクル率などのKPIを正確に測定することが、持続可能なビジネスにおいて不可欠であることを再確認させる調査結果となりました。
報告書の全文は、IBMの公式サイトにてご確認いただけます。
会社情報
- 会社名
- 日本アイ・ビー・エム株式会社
- 住所
- 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー
- 電話番号
- 03-6667-1111
トピックス(地域情報)
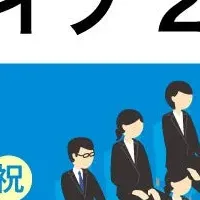
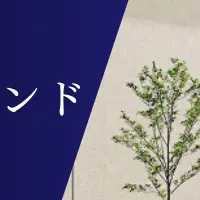

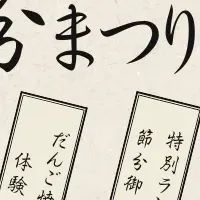
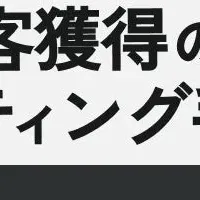
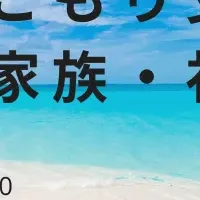
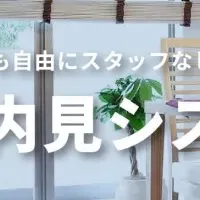
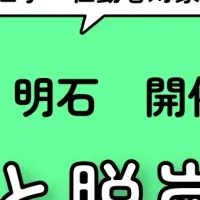


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。