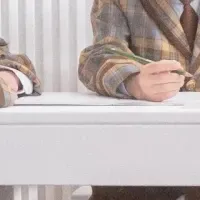

原発事故被災者支援への取り組みとその実情を知る報告会
福島第一原発事故被災者支援報告会
2023年1月9日、パルシステム連合会がオンラインで「東京電力福島第一原子力発電所事故被災者応援金」の活動報告会を実施しました。この報告会では、避難者の心のケアや居場所づくり、風化を防ぐ情報発信など、三団体の活動が紹介されました。
報告した団体とその取り組み
会の中で、以下の三団体が助成金の使途と活動内容を発表しました。
1. 市民団体ごえんのちから(横浜市旭区)
2. NPO法人フュージョン社会力創造パートナーズ(つくば市)
3. モニタリングポストの継続配置を求める市民の会・三春(福島県田村郡)
交流ツアーでつながる
市民団体ごえんのちからは、福島県南相馬市を中心に「被災地交流ツアー」を開催しています。このツアーは73回行われ、1千人以上の参加を得ています。原発事故の影響で、福島県では観光地として選ばれず、米の販売も厳しい状況が続いています。
参加者は実際に現地を訪れ、地元の人々と直にコミュニケーションを取ることで、理解を深めています。須摩代表は、自らバスを運転し、地域とのつながりを創出してきました。今年春には運転免許を返納するため、経費が増大する見込みだと語っています。「実際に足を運んでこそ、現実を知ることができる。これからも地域を支え続けていきたい」と意気込む須摩氏の言葉が印象的でした。
孤立を防ぐ取り組み
NPO法人フュージョン社会力創造パートナーズは、茨城県に避難してきた人々のために、スイーツ教室やいちご狩りなどのイベントを実施しています。このような交流の場では、参加者から「地元の言葉を聞けてうれしい」という声が寄せられています。
避難生活が続く中で、彼らは日常生活に慣れてきたものの、心の内には複雑な感情が抱えていると武田理事長は述べています。「孤独を感じる方々を少しでも支えられるよう、笑顔を絶やさずに活動を続けたい」と彼女の強い思いが伝わりました。
風化を防ぐイベント
モニタリングポストの継続配置を求める市民の会・三春では、避難者が自らの思いを語るイベント「おらもしゃべってみっか」を開催しています。このイベントは少人数で実施され、参加者が心を開きやすい環境を提供しています。そこでは時折、涙を流す人もいますが、それぞれの開催が重要な意味を持っています。
大河原共同代表は、「避難者の複雑な心情を理解し、風化を防ぐためのイベントを続けていきたい」と意気込みを語りました。
課題の乗り越え
質疑応答の場では、全三団体が「資金繰り」の困難さを挙げ、被災地域への支援が縮小している現状を懸念しています。福島の事故に対する関心が薄れている中、支援の必要性は高まっています。
パルシステム連合会の楊委員長は、「復興の兆しが見えるものの、住民の不安は依然として続いており、課題は山積みです。助成団体は、被災者に寄り添い、募金を有効活用していますので、支援のご理解をお願い申し上げます」と訴えました。
まとめ
この報告会を通じて、被災者支援の重要性と地域の実情を知ることができました。地域の復興と共に、被災者の心のケアを続けるためには、私たち一人ひとりの理解と支援が必要です。今後もこの活動に注目していきたいと思います。



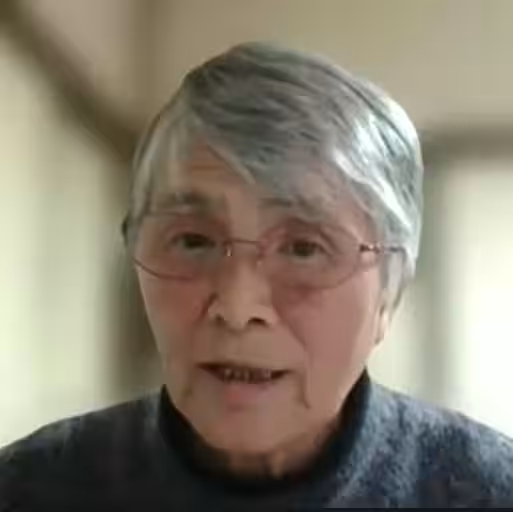

会社情報
- 会社名
- パルシステム生活協同組合連合会
- 住所
- 東京都新宿区大久保2-2-6ラクアス東新宿
- 電話番号
- 03-6233-7200
トピックス(地域情報)
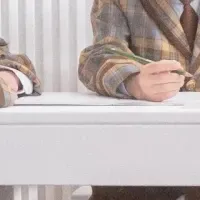


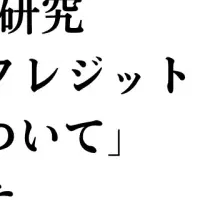

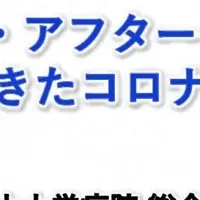

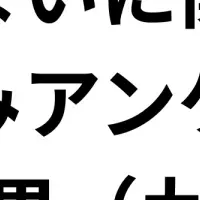

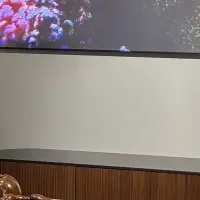
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。