
次世代計算基盤に関する調査研究の進展と評価委員会の総括
次世代計算基盤に関する調査研究の進展と評価委員会の総括
令和7年3月6日、文部科学省にて「次世代計算基盤に係る調査研究」評価委員会の第13回が開催されました。この会議では、各調査研究チームからの成果報告が行われ、最新の技術や課題について議論が展開されました。
会議の詳細
会議は、文部科学省東館の会議室でのハイブリッド形式で進行。オンライン参加も可能だったため、全国各地から専門家が集まり、活発な意見交換が行われました。出席したのは、安浦主査をはじめ、藤井孝蔵主査代理や後藤委員、その他の専門家や研究者たちです。
成果報告の主な内容
各調査研究チームは、それぞれが担当するテーマについての研究成果を報告しました。特に注目されたのは、運用技術に関する報告です。東京大学の塙教授は、冷却技術の進展について解説しました。液浸冷却の viable 性や課題についての意見が交わされ、PUE(Power Usage Effectiveness)を1.04に抑えることができる見通しがある一方で、実用化には多くの課題が残っていることが明らかになりました。
会議では冷却技術の改良についても意見が交わされ、特に高温水冷却技術が現実的かつ費用対効果の高い選択肢であるとの見解が示されました。これは、既にある技術を利用して省エネ型のシステムを構築できる可能性を示唆しています。
セキュリティの重要性
また、次世代計算基盤の運用におけるセキュリティの重要性も議論されました。特に、自然災害や電力のひっ迫に直面した際にどのように対応すべきかというトレーニングの必要性が強調されました。新たに策定されたガイドラインが、実際の運用にどのようにフィードバックされていくかが課題として浮かび上がりました。
未来への展望
今後の展望として、文部科学省の栗原室長は、「次のシステム設計においても、今回の研究成果を活かすことが重要」と述べました。また、新たな技術進展が期待される中で、3年から4年後の研究開発開始の必要性も指摘されました。
最終的に、評価委員会は、各チームからの報告を元に、今後の方向性について論じる重要な機会となりました。研究は今後も続き、次世代の計算基盤がどのように進化していくのか、専門家たちの取り組みが注目されます。
このように、次世代計算基盤に係る調査研究は、さまざまな課題を乗り越えながら、未来の技術革新に向けた貴重な一歩を踏み出していることが見て取れます。今後の成果に期待が寄せられています。
トピックス(科学)

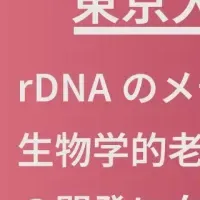








【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。