
HPCI計画推進委員会での話題は未来の計算基盤と技術変革
HPCI計画推進委員会(第63回)の概要
令和7年4月14日に「HPCI計画推進委員会」の第63回が文部科学省で開催されました。今年の委員たちは多様な専門分野から集まり、重要な議題について熱心に議論を交わしました。委員会は未来の計算基盤の整備や、技術の高度化を目指しており、参加者たちは活発な意見交換を行いました。
出席者と挨拶
会議は文部科学省の塩見局長による挨拶で始まり、各委員が自己紹介を行いました。その後、次の議題に移行し、今後の検討体制や事業計画に関する報告が行われました。委員たちは計画の進行状況に対しさまざまな質問と意見を寄せました。
議題1:今後の検討体制
田浦主査が提起した議題では、特に運用技術に関するワーキンググループの成果をどう生かしていくかが焦点となり、合田委員からも具体的な提案がありました。栗原室長は、この点に関して現在の整備体制がどのように関連しているかを解説しました。さらなる技術進化、特にGPU技術と量子コンピュータの実用化についても言及があり、非連続的な技術変化にも対応する必要性が強調されました。
産業界との連携
加えて、委員会では産業界からの参加者についても話題に上り、富士通やAMD、インテルなどの大手企業が参加していることが確認されました。ここでの議論は、次世代の計算基盤に関する調査研究を評価し、それを次のステップにどうつなげるかに焦点を当てています。
HPCIの整備計画
議論の中で特に注目されたのは、整備計画検討ワーキンググループが将来のHPCIに向けた整備計画と研究開発について討議する必要性です。委員たちは、この新たな体制がどのように運用されるかを考えることが求められています。
グローバルな視野
また、国際連携の重要性も強調され、海外の研究機関との共同研究を促進することで、日本国内の技術開発にプラスの影響を与える可能性があります。北野委員の発言にあったように、外国企業との共同研究を考慮に入れたソフトウェア戦略の構築が必要とされています。
まとめ
「富岳」の運用が2030年頃までに継続され、その後ポスト「富岳」への移行が予定されています。委員会は、新たな環境の整備や、計算科学研究の強化に向けた取り組みを行っており、全体のシステムの維持やデータ管理の重要性も認知されています。今後の議論がどのように進展し、実際の運用に結びつくのか、大いに期待されます。
最後に、事務連絡が行われ、過去の会議と同様に活発な意見交換があった本会議は無事終了しました。今後のHPCI計画に向けて、技術革新とともに進む未来への道筋が見えてきた瞬間でした。
トピックス(科学)

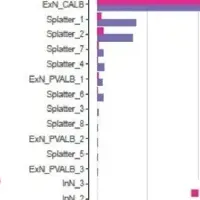

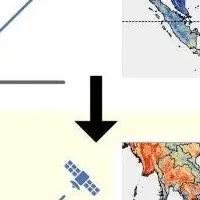
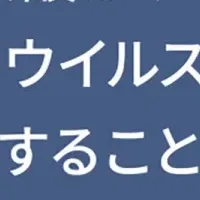




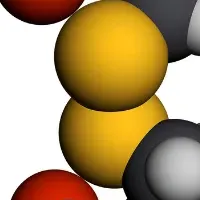
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。