
次世代計算基盤に関する調査研究委員会の振り返りと未来に向けた期待
次世代計算基盤に関する調査研究評価委員会
令和7年3月31日(月曜日)、文部科学省にて「次世代計算基盤に係る調査研究」評価委員会の第14回会合が開催されました。この会合では、これまでの取り組みを振り返り、今後の方向性について詳しく議論が行われました。
会合の詳細
会合はハイブリッド方式で開催され、文部科学省東館17階の研究振興局会議室およびオンラインでの参加者を含め、全体での議論が進められました。会議は14時から15時30分まで行われ、出席者には多くの研究者や文部科学省の職員が名を連ねました。
議題
議題は主に以下の二点でした。
1. 「次世代計算基盤に係る調査研究」における取り組みの振り返り
2. 「次世代計算基盤に係る調査研究」における検討結果の確認
取り組みの振り返り
会合の中では、特にEYストラテジー・アンド・コンサルティングが提供した資料に基づき、各委員からの意見が交わされました。高野委員の質問に対して内山氏が、NDAの締結に関する課題について説明。安浦主査は、資料作成にかかる負担を軽減し、研究者がより研究に集中できる環境づくりの必要性を提唱しました。
次世代計算基盤に関する検討結果
また、議論の中では、システム開発において単発的な調査研究にとどまらず、継続的かつ機動的な支援事業の必要性が強調されました。AI技術の急速な発展に対抗するために、国として長期的な視点が求められるとの意見もありました。これにより、次世代計算システムの開発体制の重要性が再認識されました。
現在と未来の見通し
この委員会は、3年間の調査および研究活動を経て、次世代計算基盤の開発に向けた具体的な方針を定める契機となりました。会議の参加者たちは、これからの研究環境の整備や計算科学技術の振興について期待を寄せています。特に、量子コンピュータとの統合、AIを活用した計算基盤の進化は、今後の研究の基盤を形作る上で大きな影響を与えることでしょう。
そこで文部科学省においても、さまざまな科学技術の分野に貢献できるような研究を続けていくための体制を整える必要があるとの考えが強調されました。特に、次世代の計算基盤が日本の未来のために必要不可欠であることを委員たちが再確認した議論の成果は、今後の政策においても重要な指針となっていくでしょう。
まとめ
次世代計算基盤に係る調査研究評価委員会の第14回会合は、過去の活動を振り返りつつ、未来に向けた新たな展望を示す機会となりました。これからも日本の科学技術の発展を支えるため、委員たちは積極的に意見を交わし合い、よりよい基盤を築いていくことが求められます。
トピックス(科学)

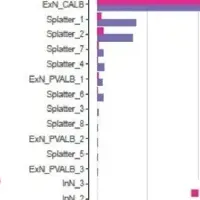

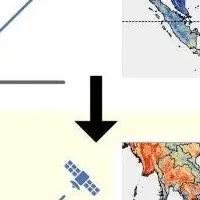
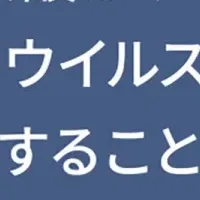




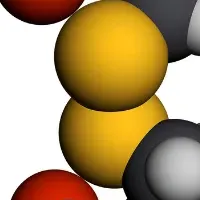
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。