

日産とTBWA HAKUHODOが手掛ける、動物保護の革新プロジェクト「NISSAN ANIMALERT」
日産とTBWA HAKUHODOの取り組み
日産自動車と株式会社TBWA HAKUHODOが共に手掛ける「NISSAN ANIMALERT」は、電気自動車(EV)の音を活用した革新的なプロジェクトです。この取り組みは、車両と野生動物の接触事故、いわゆるロードキルのゼロを目指しています。特に注目されるのは奄美大島と徳之島にのみ生息する絶滅危惧種のアマミノクロウサギを保護対象としています。
このプロジェクトは、3月3日の「世界野生生物の日」に合わせて発表され、日産の公式YouTubeチャンネルや各種SNSでのムービー公開が行われました。プロジェクト名の「NISSAN ANIMALERT」は、動物(ANIMAL)と警告(ALERT)を組み合わせたものです。ここでは、歩行者に車の接近を知らせるために開発されたEVの音をさらに進化させ、野生動物の交通事故を減少させようという狙いがあります。
プロジェクトの発想と背景
プロジェクトのきっかけは、日産自動車が2010年に世界初の量産EV「日産リーフ」に装備した接近通報音技術です。この技術は、クルマが接近する際の音を周囲に知らせるもので、歩行者の安全を確保するために重要な役割を果たしています。プロジェクトチームは、この技術を応用して、動物に特化した周波数の音を発する装置を開発し、これをクルマに搭載することで、動物たちに注意を促す仕組みを目指しています。
特に、アマミノクロウサギの保護が重要視されています。この種は日本固有で、絶滅危惧IB類に指定されており、影響が深刻です。国土交通省によると、2022年度には数万件ものロードキルが発生しており、そのほとんどがイヌやネコ、タヌキ、そしてシカなどです。これに対し、奄美大島でのアマミノクロウサギのロードキル件数が急増しており、2023年には過去最多を記録しました。
具体的な施策と実施
「NISSAN ANIMALERT」では、まずアマミノクロウサギのロードキル数を減少させることを目指し、今後の全国展開に繋げる計画を立てています。その第一歩として、奄美大島での走行実験を予定しています。日産テクニカルセンターでの高周波音の特性分析を経て、2024年12月からは実証実験車両でのデモ走行が始まります。これにより、アマミノクロウサギがどのように反応し、逃げることができるかを確認する予定です。
プロジェクトの意義
このプロジェクトは、日産自動車のマーケティング、広報だけでなく、開発部門や学術機関、自治体など、幅広い参加者が協力して進めている点が特徴です。異なるバックグラウンドを持つメンバーたちが集まり、動物と人間の共生のための技術として、この取り組みは進化しています。日産が掲げる「Zero emission, zero fatalities.」の理念に賛同し、道路での事故を一つでも減らすために、クルマの音の重要性を再認識し、積極的に解決策を模索しています。
「人を守る音から、動物を守る音へ」というキャッチコピーを掲げるこのプロジェクトは、動物愛護の新たなスタンダードを作る可能性を秘めています。日常生活の中で、こうした技術が利用されることで、私たちの身近な環境がより安全なものになることを期待しています。今後の進展に目が離せません!




会社情報
- 会社名
- 株式会社TBWA HAKUHODO
- 住所
- 東京都港区芝浦1-13-10
- 電話番号
- 03-5446-7386
トピックス(地域情報)




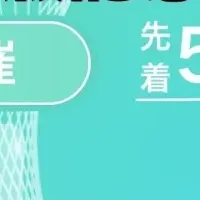
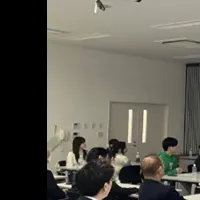




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。