

多摩川流域を食で巡る!「おいしい流域」イベントが7月30日からスタート!
多摩川流域を舞台に食で巡る学びの旅「おいしい流域」イベント
一般社団法人おいしい未来研究所が主催する「おいしい学校」プロジェクトの一環として、7月30日から「おいしい流域」イベントがスタートします。このイベントは、次世代へ豊かな海を引き継ぐため、食を通して山から海までの繋がりを学び、海を介して人と人とのつながりを深めることを目的としています。
「おいしい流域」では、多摩川流域を舞台に、水と人々の暮らしが織りなす歴史や文化、自然環境を、食を通して体験できます。全6回のイベントを通して、山の湧水から始まり、川上、そして海へと、流域を下っていくことで、水と共に人々が築き上げてきた食文化や自然環境、土地の歴史や文化を深く理解することができます。
イベント内容
第1回「源流の冷たい水は、海からやってきた」(7月30日)
檜原村にて、東京裏山ワンダーランド代表 ジンケンさんと(一社)アナドロマス代表理事・清田直博さんをナビゲーターに、水の路(みち)が始まる山からスタートします。湧水を汲み、水との暮らしを体験することで、山から海までのつながりを体感します。
第2回「あゆが減って、ふたたび増えたわけ」(8月6日)
奥多摩川にて、東京サクラマスプロジェクト 菅原和利さんをナビゲーターに、遡上する魚を釣り、食べるという体験を通して、川と海の生態循環を学びます。天然あゆが減った理由や、天然と放流の違いなどを学び、川と海のつながりを理解を深めます。
第3回「のりと、トイレの、密接な関係」(9月14日)
大田区大森にある大森海苔ふるさと館にて、江戸料理研究家 うすいはなこさんをナビゲーターに、海苔生産の歴史と現在を学びます。海苔の成長に必要なミネラルなどの養分が、山から川を伝って海に流れ込むことを知り、海の恵みの大切さを体験します。
第4回「わさびを育むたくさんの小さな源流」(9月28日)
調布市深大寺にある神代農園にて、文脈デザイン研究者/「食とアミニズム」著者 玉利康延さんをナビゲーターに、湧水と生活の関係について探ります。湧水豊富な場所でのわさび栽培の歴史や文化、地域の暮らしについて学び、湧き水からの恵みを体感します。
第5回「なまずが教えてくれる多摩川の今」(日時調整中)
都内にて、江戸料理研究家 うすいはなこさんをナビゲーターに、なまずが重要な食料源であった江戸時代の暮らしを学びます。食料の輸送や保存技術が未発達だった時代に、人々はどのように魚を食していたのか、当時の暮らしに思いを馳せます。
第6回「すずきさんは海と川のあいだで暮らす」(10月20日)
千葉県船橋市にて、日本サステナブルシーフード協会代表/「おさかな小学校」校長 鈴木允さんとスズキ漁師 大野和彦さんをナビゲーターに、東京湾で暮らす「すずき」について学びます。川と海が混じり合う汽水域でのすずきの生態や、東京湾でのすずき漁について学び、川と海のつながりを理解を深めます。
※ 全6回シリーズですが、どの回も単発で参加できます。
※ 本プログラムは、日本財団 海と日本PROJECTの一環として開催されます。
イベントへの参加方法
「おいしい流域」公式ホームページから、各回の申し込みフォームにアクセスして申し込んでください。
「おいしい学校」について
「おいしい学校」は、食体験を起点にした講義やフィールドワークを通じて、食にまつわる様々なテーマを探求する場です。食の裏側にある歴史や文化、テクノロジーや自然環境など、多様な視点をつなぎ合わせることで、新たな問いを生み出し、食から考える社会や未来をつくる活動を作っていくことを目指しています。
日本財団「海と日本PROJECT」について
日本財団「海と日本PROJECT」は、海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。
お問い合わせ
[email protected]
「おいしい流域」を通して、食と自然環境、そして人とのつながりについて学び、豊かな未来を創造しませんか?



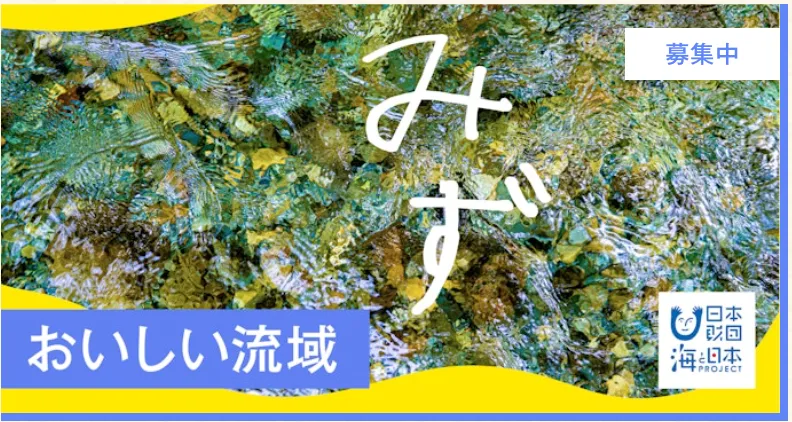






トピックス(地域情報)







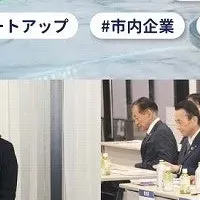


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。