

立命館大学に宇宙地球探査研究センターが設立される意義とは
立命館大学宇宙地球探査研究センター(ESEC)設立の背景と意義
2023年に立命館大学に新たに宇宙地球探査研究センター(ESEC)が設置され、センター長には総合科学技術研究機構の佐伯和人教授が任命されました。これにより、同大学には25名以上の研究者が集結し、共同でさまざまな研究に取り組む体制が整いました。センター設立の目的は、人類の生存圏の維持と拡大に貢献するという壮大なビジョンの下、宇宙探査や開発へ向けた新たなアプローチを導入することにあります。
新しい宇宙研究のフェーズ
近年、NASAのアルテミス計画や欧州宇宙機関(ESA)の「Moon Village構想」(2050年に月に1000人規模の村を作る計画)など、宇宙における研究開発が加速しつつあります。日本における宇宙研究は、これまでは発見型の探査に長けていましたが、この新しいセンターは「探査拠点開発」に特化し、人類が宇宙で生存するための最初のステップを踏み出すことを目指しています。
発見型探査を「第一フェーズ」、探査拠点開発を「第二フェーズ」、そして将来的な宇宙における都市開発を「第三フェーズ」と位置付けた場合、ESECは世界でも珍しく、日本においては初めてとなる「第二フェーズ」に専念する研究組織です。このような研究活動は、人跡未踏の地に自ら探査・開発拠点を設立するという使命を持ち、最先端の観測データの提供を果たすことを目標としています。
JAXAとの連携と今後の展開
日本の宇宙研究機関であるJAXA(宇宙航空研究開発機構)もさまざまなプロジェクトを進行中です。特に、小型月着陸実証機プロジェクト(SLIM)の実施や、月極域の水資源を探るLUPEXミッションが来年度以降に予定されています。これらのプロジェクトには佐伯センター長が主要メンバーとして携わっています。
ESECでは、月や火星を主要な研究フィールドとして、「宇宙資源学の創成」に挑戦します。具体的には、SLIMやLUPEXの搭載機器の開発・運用、さらには月面基地建設に関する地質調査技術の研究などが行われる予定です。さらには、地球上でのフィールド探査においても日本有数の拠点となることを目指します。
産業界との連携を強化
このセンターでは、多様な企業との連携を強化し、宇宙探査に関連するイノベーションを創出することを目標に掲げています。これにより、月や惑星を研究フィールドとしながら、社会への実装を見据えた研究活動を進めていく計画です。
新設されたESECは、これから宇宙研究において重要な役割を果たすことが期待されています。これにより、われわれの目の前に広がる宇宙の謎を解明し、人類の生存圏の拡大に向けた探求が進むことでしょう。公式ウェブサイトは6月29日に公開予定で、今後の展開が楽しみです。
- - ESEC公式WEBサイト: こちら
- - お問い合わせ先: 立命館大学 広報課(TEL:075-813-8300、E-mail:[email protected])
会社情報
- 会社名
- 立命館大学
- 住所
- 京都府京都市中京区西ノ京朱雀町1立命館朱雀キャンパス
- 電話番号
- 075-813-8146
トピックス(科学)




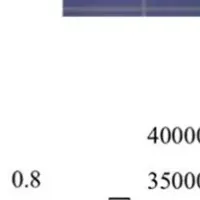
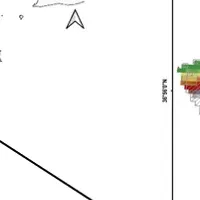
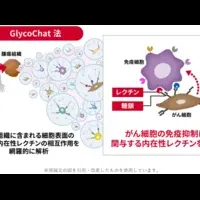
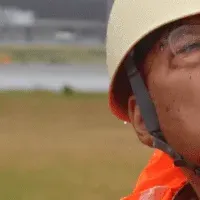


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。